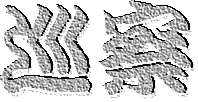偮偄偵偭丄偮偄偵偭夛捗偱偡両夛捗偵峴偒偨偄偭峴偒偨偄偭偲尵偄懕偗偰
傗偭偲丄傗偭偲夛捗弰嶡寛峴偱偡両乧偲偄偭偰傕崱夞偼偐側傝搨撍偵椃峴偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅
偲偄偆偺傕丄愘幰偑乽弔偵偼敓娰偵傕峴偗偨偟丄側傫偩偐傫偩偱枅寧嫗搒偵傕懌傪塣傋偰偄傞偟丄
崱擭偼戝壨Year両條條偩偹偭丅偙偺暘偠傖壞偁偨傝偵偼夛捗偵峴偗偪傖偄偦偆偠傖側偄丠丠乿
乧側傫偰忕択傔偐偟偔壗搙傕尵偄懕偗偰偄偨偐傜偐傕偟傟側偄偺偱偡偑丄杶媥傒傪峊偊偰媫绡
擇廫擔慜偵晝忋偑夛捗椃峴寛峴偺GO僒僀儞傪弌偟偨堊偵擇廫擔偱椃峴傪寁夋偡傞偙偲偵乧丅
偲偄偆傢偗偱丄崱夞偺弰嶡偼晝忋偑懌傪堷偒庴偗偰偔傟偨偺偱儗儞僞僇乕偱偺巎愓弰傝偱偡v
偑丄擇廫擔偲偄偆尷傜傟偨帪娫偱椃峴傪寁夋偡傞愘幰偼昁巰偱偟偨(*丵*丟
杶媥傒慜偲偄偆偙偲偱巇帠傕偓傝偓傝偪傚偭傉側帪偩偭偨偺偱偡偑丄拫媥宔偵偼巎愓傪HP偱妋擣丄
梉媥宔偵偼廻偺梊栺乧偲偄偆嬶崌側擔傪懕偗傞偙偲廫擔娫丄丄丄偳偆偟傛偆傕側偔側偭偰崱夞丄
戝曄屼悽榖偵側傝傑偟偨偺偑怴愶慻僒僀僩乽枊枛怴慖慻曠忣乿偺娗棟恖傝偊條丅
傝偊條偺椃峴婰偵偼乽偙傟偐傜朘偹傞曽傊偺屼埬撪乿偑偲偰傕徻偟偔捲傜傟偰偁傝丄
偟偐傕幵偱偺堏摦傪庡偵偝傟偨傕偺偱丄崱夞偺愘幰偺弰嶡偵偼惁偔偁傝偑偨偄忣曬枮嵹偱偟偨丅
憗懍丄傝偊條偵傕僐儞僞僋僩傪庢傜偣偰捀偄偰丄拝乆偲椃掱傪楙傝懕偗丄偄偞敧寧幍擔両弌恮両
壼埼椃峴偐傜嶰儢寧丅傑偝偐偙傫側偵憗偔丄傑偨旘峴婡偵忔傞偙偲偵側傠偆偲偼乧丅
AM侾侾丗侽俆丄埳扥嬻峘敪丅偁偭偲偄偆傑偺僼儔僀僩偱丄AM侾俀丗侾侽丄柍帠偵暉搰嬻峘拝丅
梊掕偱偼PM侾丗侽侽偐傜儗儞僞僇乕偺梊栺傪偟偰偄偨偺偱偡偑丄嬻峘偵傕偆儗儞僞僇乕偺
偍孼偪傖傫偑僗僞儞僶僢偰偔傟偰偄偨偺偱丄憗懍僇儘乕儔NCV偵忔傝崬傒丄
嵟弶偵岦偐偆偼敀壨彫曯忛両乧偲丄傑偢偼僇乕僫價偺巊偄曽偐傜偮傑偯偔恊巕擇恖(T傊T丟(T傊T丟
僇乕僫價偺愢柧彂偲抧恾傪椉庤偵傑偢偼愘幰偺儅僯儏傾儖僫價偱偲偵偐偔弌敪両
 傑偢偼拫怘挷払偺堊偵棫偪婑偭偨僐儞價僯偱
傑偢偼拫怘挷払偺堊偵棫偪婑偭偨僐儞價僯偱
暉搰弶偺價僢僋儕傪懱尡乮徫丅傔偪傖偔偪傖挀幵応偑峀偄偱傗傫偺乧(邅∵丟(邅∵丟丅
傐偐乕傫偲岥偑敿奐偒忬懺偺恊巕擇恖乮徫丅戝嶃偠傖偁傝偊傑偣傫丅
側傫偣僩儔僢僋偑俆戜傕俇戜傕晛捠偵掆傔傜傟傞偔傜偄峀偄傫偩傕傫丅
搚抧傕峀偄偐傜偱偟傚偆偑丄寛峴僩儔僢僋偺墲峴傕懡偄堊側偺偱偟傚偆偑丄
嬃偒傑偟偨丅丅丅偦傫側傢偗偱攦偄崬傫偩僷儞傪傁偔偮偒偮偮丄
撍慠偺棆塉偵傔偘偦偆偵側傝側偑傜傕丄僇乕僫價偵摫偐傟偰
幵傪憱傜偣傞偙偲堦帪娫丅PM侾丗係侽丅彫曯忛摓拝丅
僗僐乕儖偺傛偆側塉傪愽傝敳偗偰撥傝偑偪側嬻柾條偱偟偨偑丄
側傫偲傕乽晽塤媫傪崘偘傞乿傛偆側暤埻婥傪忴偟弌偟偰偄傞傛偆偱
偦傫側暤埻婥偵悓偄側偑傜搊忛乮徫丅
崱偱傕傛偔峛巕墍偱搶杒偺崅峑偑桪彑偟偨傝偡傞偲丄乽桪彑婙偑敀壨偺娭傪墇偊傞乿
偲昞尰偝傟傑偡偑丄屆偔偼敀壨偺娭傛傝杒偑墱廈丒壼埼丅
娭偼杒傊偺旛偊偲偝傟偰偄傑偟偨偑丄峕屗婜偵娭偵戙傢偭偰娭搶偲搶杒偺娭栧偲偟偰丄
偙偺彫曯忛乮敀壨忛乯偼墱廈傪庣傞偵傕峌傔傞偵傕愴棯揑偵廳梫側応強偱偟偨丅
曡扖愴憟偵偍偗傞敀壨岥偺愴偄傕偙偙偐傜巒傑傝傑偟偨丅
 宑墳巐擭乮侾俉俇俉乯塠巐寧擇廫擔丄偙偺忛傪夛捗斔暫偑扗庢丅
宑墳巐擭乮侾俉俇俉乯塠巐寧擇廫擔丄偙偺忛傪夛捗斔暫偑扗庢丅
擇廫擇擔偵偼嵵摗堦夵傔嶳岥師榊傪戉挿偲偡傞怴愶慻偑敀壨忛壓偵擖傝丄
敀壨奨摴増偄偺敀嶁岥偺娭栧傊攝偝傟偰丄擇廫屲擔偺枹柧丄
敀壨奨摴傪恑傫偱偒偨怴惌晎孯偲傇偮偐傝丄弿愴偼抧偺棙傪摼偰彑棙丅
偟偐偟屲寧堦擔丄寖愴偺偆偪偵幍昐柤傕偺巰幰傪弌偡戝攕杒丅
彫曯忛棊忛屻丄怴愶慻傕夛捗斔椞偵嬤偄惃帄摪廻傑偱攕憱偡傞偙偲偵乧丅
偙偺帪偺暫壩偱敀壨忛偺寶暔偼慡偰從幐偟偰偟傑偭偨堊丄
崱偺彫曯忛偼暯惉嶰擭偵屆抧恾傪嶲徠偟側偑傜
杮奿揑偵暅尦偝傟偨傕偺偱偡丅彫崅偄壀偵悧抎幃偵憿傜傟偨暯嶳忛丅
暅尦偝傟偨嶰廳楨偼崅偝偑栺侾係儊乕僩儖偺旤偟偄僼僅儖儉偱偡丅
偑丄拲栚偡傋偒偼忛撪偺拰傗彴斅丅偦偙偵偼揝朇偺抏嵀偑乧(邅∵)
偲偄偆偺傕丄傟傜偺悪嵽偼敀壨岥偺峌杊愴偑孞傝峀偘傜傟偨
堫壸嶳偐傜敯嵦偟偨傕偺偱丄摉帪傪幟偽偣傞彎嵀偱偟偨丅
愘幰傕晝忋傕曡扖愴憟偵夵傔偰巚偄傪抷偣偰偄傞偲丄
偙偙偱揤庣妕擖傝岥偱學堳傪偝傟偰偄偨偍偠條払偲傕怴愶慻丒枊枛榖偵
壩偑晅偄偰乮徫乯丄尦怴愶慻戉巑偱偁偭偨惔尨惔偝傫偺偍曟嶲傝偵傕
峴偒偨偄巪傪崘偘傞偲丄抧恾傪彂偄偰偔偩偝偄傑偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡両
 惔尨惔偲偼杮柤偼惣懞栱嶰塹栧丅孎杮斔偺扙斔幰偱丄
惔尨惔偲偼杮柤偼惣懞栱嶰塹栧丅孎杮斔偺扙斔幰偱丄
宑墳尦擭偵峕屗偱怴愶慻偵擖戉偟偨帪偵惔尨惔傪柤忔傝丄
崅戜帥搣偵婑梌偟偰戉傪棧傟丄桘彫楬偺曄偺屻偼嶧杸斔偵懏偟偰
晲愳捈巬偺柤偱敀壨岥偺愴偄偵嶲愴丅敀嶁娭栧偱摙巰偟丄
庱傪敀壨忛壓偵偝傜偝傟偨偲偄偄傑偡丅偟偐傕偙偺晲愳捈巬丄
斅嫶偱嬤摗桬偺惓懱傪尒攋偭偨偆偪偺堦恖偩偭偨偲偐偱丄丄丄
惔尨惔傪抦傞怴愶慻戉巑傕丄嶯偝傟偨晲愳偺庱傪尒偨偐傕偟傟側偄偲巚偆偲丄
偳偆偵傕傗傞偣側偄巚偄偑偟偡偹丅丅丅
偦偺晲愳捈巬偝傫偺偍曟偱偡偑丄彂偄偰栣偭偨抧恾傪棅傝偵丄
搶偺忛栧傪弌偰摴側傝偵杒傊懌傪岦偗傟偽丄彫曯忛偺棤庤偵偁傞
捔岇恄嶳偺乽曡扖嶧杸斔愴巰幰擵曟乿偵崌憭偝傟偰偄傑偡丅
偑丄丄丄偙偺捔岇恄嶳傊偺擖傝岥偐傜偟偰偪傚偭偲晐偄応強偱偡丅PM俀丗侾俆丅
敄埫偔偰嵶偄廱摴偺傛偆側嶁摴傪搊傟偽丄捀忋偵彮偟奐偗偨応強偑偁傝丄
偦偙偵崌憭偺曟愇偑捔嵗偟偰偁傝傑偡丅偑丄傗偼傝敄埫偔偰晐偄偱偡丅
乽偙傫側強丄彈偺巕偑堦恖偱偔傞傛偆側僩僐偠傖側偄両乿偲敿暘崢偑堷偗偰偄傞晝忋丅
乽偩偐傜堦弿偵棃偰傕傜偭偰傫偠傖側偄偺偝丅乿偲愘幰丅乧恊巕懙偭偰彫怱幰偱偡丅
曟愇偺壓偺戜嵗偵愴巰幰奺乆偺愴巰偺応強丄強懏戉丄巵柤偑
婰偝傟偰偄傞偺偱偡偑丄晲愳捈巬偺柤偼惓柺岦偐偭偰堦斣塃抂偺
榞撪塃偐傜巐斣栚偵妋擣偱偒傑偟偨丅崌彾丅丅丅
捔岇恄嶳傪屻偵挀幵応偵岦偐偭偰傕偲偒偨摴傪栠傟偽丄婥晅偄偨
愇奯偺晄巚媍側柾條丅廳偝偵懴偊偐偹偰偐攇懪偭偰偼偄傑偟偨偨偑
偦偺愇偺慻傒曽偑柧傜偐偵嶌堄揑側儌僓僀僋柾條偺鉟楉側愇奯丅
尦乆丄彫曯忛偼墱塇偺埳払巵丄忋悪巵側偳偺奜條戝柤傪
揋偲偟偨嵺偺忛側偺偱杒懁偺杊屼偑廳帇偝傟偰偄傑偡丅
忛偺杒懁偵偼垻晲孏愳偑棳傟偰偄傞偺偱丄杒偺嵟弶偺杊屼偼偙偺垻晲孏愳丅
戞擇偺杊屼偑敀壨忛偺杒丒搶丒惣偺嶰曽偵旛偊偨悈杧丅
偦偟偰戞嶰偺杊屼偑敀壨忛偺摿挜偱柺敀偄擇抜峔偊偺愇奯偱偡丅
幚嵺丄彫曯忛棊忛屻丄墱塇楍斔偺摨柨孯偼壗搙傕扗娨傪帋傒傑偟偨偑丄
怴惌晎孯偺悢攞偺愴椡偱峌傔偨偺偵傕娭傢傜偢丄偙偺愇奯偵慾傑傟偰
昐擔偵媦傇敀壨岥偺愴偄偱偮偄偵扗娨偡傞偙偲偽偱偒傑偣傫偱偟偨丅
偝偰丄彫曯忛傪屻偵偟偰師偵岦偐偄傑偟偨偺偼挿庻堾丅
惣孯偺宑墳曡扖弣崙幰暛曟丄敀壨栶恮朣彅巑旇偑偁傝傑偡丅PM俁丗侾侽丅
敀壨愴偵偍偗傞挿廈丒搚嵅丒戝奯丒嵅搚尨丒娰椦摍奺斔偺愴杤幰傪
杽憭偟偨傕偺偱丄尦乆偼嶧杸斔偺愴杤幰傕杽憭偝傟偰偄偨偺偱偡偑丄
愭掱偺捔岇恄嶳偵夵憭偝傟傑偟偨丅
偙偺挿庻堾丅側偐側偐暘偐傝偯傜偄応強偵偁傝傑偡丅
僇乕僫價偵埬撪偟偰傕傜偭偨傕偺偺丄偪傚偆偳偙偺擔丄壴壩嵳偱偁偭偪偙偭偪偑
摴楬晻嵔偝傟偰偄偰丄丄丄偝傜偵偙傜偊偒傟側偔側偭偨偐偺傛偆偵
偄偒側傝偺僗僐乕儖(T仭T丅儚僀僷乕慡奐偵偡傞傕偺偺暐偄愗傟側偄偔傜偄偺戝塉偱
偟偽偟嬤偔偺昦堾偺挀幵応偵偰塤愗傝偺媀傪帋傒傞偙偲偵丅丅丅乽偁乕傔乕傗乕傔乕両乿
 20暘偔傜偄擲偭偰偄偨傜師戞偵彫塉偵側偭偨偺偱
20暘偔傜偄擲偭偰偄偨傜師戞偵彫塉偵側偭偨偺偱
挀幵応偐傜曕偄偰杮挰捠傝傪惣傊丅
塃庤傪拲堄偟偰曕偗偽乽宑墳曡扖弣崙幰暛曟乿偲彂偐傟偨
挿庻堾偺敀偄棫偰嶥偑偁傞偺偱丄埬撪偵廬偭偰榚摴傪恑傔偽
挿庻堾嫬撪偺庤慜偵杽憭曟抧偑偁傝傑偡丅
愭掱偺塉偱曟抧偼悈怹偟忬懺偩偭偨偺偱拞偵擖傞偙偲偼
弌棃側偐偭偨偺偱偡偑丄墦栚偵尒傞偲堦恖堦恖偺曟偑寶偰傜傟偰偄偰丄
巵柤偺忋偵乽姱孯乿偲擖偭偰偄傑偟偨乧丅
偪傚偭偲偙傟偵偼乽乧乧乧丅乿偲愨嬪偝偣傜傟傑偟偨偑丄丄丄
敀壨愴偺屻丄敀壨偺恖乆偼愴杤暫巑偨偪傪搶惣孯傪栤傢偢偵憭傜傟偨傛偆偱
搶惣椉孯偺愴杤幰偺曟旇丒嫙梴旇偼丄敀壨巗撪偩偗偱傕俆侽埲忋偁傞偲偺偙偲丅
偙偺挿庻堾偵偼惣孯懁偑傑偲傔偰憭傜傟偰偄傑偡偑丄搶孯愴巰幰偺嫙梴旇偼
愴摤応強偲側偭偨巗奨抧偺偁偪偙偪偵嶶嵼偟偰偄傑偡丅堦偮堦偮傑傢傞偺偼
寢峔崪偱偡偹丅丅丅崱夞偼尷傜傟偨帪娫偱偟偨偺偱嬤娫偩偗夞傞偙偲偵偟傑偡偑
偄偮偐偼敀壨廃曈偠偭偔傝扵嶕偟偨偄偲巚偄傑偡丅偲偄偆傢偗偱丄師偼椬偺榚杮恮傊丅
 椬偲偄偭偰傕丄愭偺杮挰捠傪偦偺傑傑惣傊懌傪岦偗傞偺偱偡偑丄
椬偲偄偭偰傕丄愭偺杮挰捠傪偦偺傑傑惣傊懌傪岦偗傞偺偱偡偑丄
偙傟傑偨惁偔嵶偄榚摴偺墱偵偁傞堊偵丄拲堄偟偰恑傑側偄偲嬋偑傝懝偠傑偡丅
乽杮恮乿偼戝柤丄枊棛丄捄巊側偳偺廻幧偱偡偑丄
乽榚杮恮乿偲偼杮恮偵師偖奿幃偺椃饽偺偙偲丅
敀壨岥偺愴偄偱偼丄偙偺榚杮恮偺乽桍壆乿偑怴慖慻偺廻幧偲偝傟丄
嵵摗堦傪偼偠傔偵昐榋柤偑廻攽偟偨偦偆偱偡丅
桍壆偼丄屻偺柧帯廫巐擭偺柧帯揤峜搶杒弰岾偺嵺丄
墲楬偼媥宔強偲偟偰丄婣楬偼廻攽偝傟偨廻偲偄偆偙偲偱偡丅
梻擭丄戝壩偱桍壆傕旐奞傪庴偗偨傕偺偺丄
柧帯揤峜偺峴嵼強偵偁偰傜傟偨憼嵗晘偺搚憼偼從幐傪柶傟丄
乽柧帯揤峜峴嵼強愓偺旇乿偲偲傕偵寶偭偰偄傑偡丅
偝偰丄杮挰捠傪偦偺傑傑捈恑偟偰嵍庤偵愜傟傟偽搆曕屲暘傎偳偺応強偵
峜摽帥偑偁傞偺偱偡偑丄丄丄傑偨偟偰傕塤峴偒偑夦偟偔側偭偰偒偨堊偵
媫偄偱幵傊旔擄偡傞偙偲偵丅偲偄偆傢偗偱媏抮墰偝傫偺屼曟嶲傝偼傑偨師夞(T仭T丅
場傒偵媏抧墰偝傫偲偼怴愶慻戉巑偱偡丅峜摽帥偵偼乽愴巰恖嫙梴偺旇乿偺墶偵丄
敀壨岥偺愴偄偱愴巰偟偨媏抧偝傫偺偍曟偑暲傫偱寶偭偰偁傞偦偆偱丄
尰嵼傕庤岤偔挗傢傟偰偄傞偲偺偙偲偱偡丅
幵偵摝偘崬傓偲摨帪偔傜偄偵偳偳偳乕偭偲嵞搙崀傝弌偟偨戝塉丅
偟傚偆偑側偐偭偨偺偱梊掕曄峏偱慜弎偺乽敀壨偺娭乿傊峴偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅
導摴76崋慄傪幵偱撿壓偡傞偙偲20暘偽偐傝丅嶳娫傪憱傝敳偗傞摴偱偡偑丄
抧恾傪尒傟偽敀壨偺撿懁偺抧宍偼彫嶳側偑傜傕偨偔偝傫偺嶳偑楢側傞嶳妜抧懷丅
愄傕崱傕娭搶偐傜懕偔奨摴偼偄偢傟傕嶳偺娫傪朌偆傛偆偵憱偭偰傞偺偱丄
偙傟傜偺彫嶳傪墴偝偊傟偽摢忋偐傜奨摴傪峌寕偱偒傞傢偗偱丄
愭偺敀壨岥偺愴偄偺愢柧偱乽抧偺棙傪摼偰偺彑棙乿偲偄偆偺偼偙偺偙偲偩偲幚姶丅
 PM俁丗俆侽丅偝偰敀壨偺娭偱偡偑丄偙傟偼乽娭乿偱偼偁傝傑偡偑
PM俁丗俆侽丅偝偰敀壨偺娭偱偡偑丄偙傟偼乽娭乿偱偼偁傝傑偡偑
峕屗帪戙偺娭強偱偼側偔丄俇係俆擭偺戝壔偺夵怴偺帪偺暥專偵偁傞帠偐傜丄
偦偺崰偵壼埼偺撿壓傪杊偖堊偵寶偰傜傟偨嵲偩偭偨偲悇應偝傟偰偄傞傛偆偱丄
俉乣俋悽婭崰偵婡擻偟偰偄偨傛偆偱偡丅仼晄曌嫮側帪戙側偺偱傛偔夝傝傑偣傫丅
暯埨枛婜偵塰偊偨墱廈摗尨巵偺椞搚偺嫬奅偱偁傝丄
尮媊壠丄尮媊宱傕偙偙偐傜搶杒傊擖偭偨偲偄偆偙偲偱丄
摿偵壧枍偵撉傑傟傞偙偲偑懡偔丄懡偔偺暥壔恖偑偙偺抧傪朘傟偰偄傑偡丅
桳柤強偱徏旜攎徳傕偦偺堦恖丅
偟偐偟丄傗偑偰敀嶁墇偊偲偄偆摴偑庡偵巊傢傟傞傛偆偵側傝丄
偄偮偟偐朰傟嫀傜傟偰嬐偐偵揱彸偺拞偵敀壨娭偑揱偊傜傟傞傛偆偵丅丅丅
偦偟偰屻偵敀壨斔庡偱偁偭偨徏暯掕怣偑敀壨娭傪偙偙偩偲掕傔偰丄
尰嵼抧偵旇傪寶棫偟偨偲偄偆偙偲偱丄尰嵼偺敀壨娭偑偁傞偲偄偆師戞丅
 奒抜傪忋傝偒偭偨墱偵偁傞敀壨恄幮偺懠偵暅尦偝傟偨傕偺偼側偔丄
奒抜傪忋傝偒偭偨墱偵偁傞敀壨恄幮偺懠偵暅尦偝傟偨傕偺偼側偔丄
愭傎偳偺徏暯掕怣寶棫偺旇偲丄嬻杧偑墲帪傪偟偺偽偣偰偄傑偡丅
崙巜掕巎愓偲偝傟偰偄傞偩偗偁偭偰丄側偐側偐帪戙傪姶偠偝偣傜傟傞応強偱偟偨丅
偝偰偝偰丄尦棃偨摴傪栠偭偰偄偞夛捗庒徏傊両嵵摗偝傫偺懌庢傝傪捛偆傛偆偵
惃帄摪摶偵帄傞敀壨偐傜偺嵟抁儖乕僩丄敀壨奨摴乮堬忛奨摴乯偱偁傞
崙摴俀俋係崋慄傪傂偨憱傝傑偡丅傇偄偄乣傫丅
奨傪屻偵偡傟偽偡偖嶳娫偵側傝丄僇乕僫價偺埬撪偩偗傪棅傝偵
惃帄摪摶傪栚巜偟傑偡丅敀壨偺愴偄偵傗傇傟偰戅偄偨応強偲偄偆偙偲偱丄
婥帩偪偼屻傠傪怳傝曉傝怳傝曉傝偟側偑傜丅丅丅
傗偑偰嶳傕墱怺偄応強偵側傝丄幵偺捠傝傕庘偟偔側偭偰偒偨偁偨傝偱
惃帄摪摶偵偝偟偐偐傝傑偟偨丅PM係丗侽侽丅
 偙傫側仺偺娕斅偑偁偭偨偺偱栴報偺巜偡傑傑偵嵍傊愜傟偰憱傞偙偲侾侽暘丅
偙傫側仺偺娕斅偑偁偭偨偺偱栴報偺巜偡傑傑偵嵍傊愜傟偰憱傞偙偲侾侽暘丅
屆偄壠偑棫偪暲傇戃彫楬偵撍偒摉偨偭偰偟傑偄傑偟偨丅丅丅
摶偭偰乧偳偙傜傊傫偑摶偭偰妋掕偝傟偰側偄傫偱偟傚偆偐丠丠
傛偔暘偐傜側偄側傝偵傕乽傑偀偙偙傜傊傫乿偭偰偙偲偩偗報徾晅偗偰偒傑偟偨丅
戃彫楬側忋偵僇乕僫價偵側偄摴柍偒摴傪恑傫偱偄偨堊偵丄巇曽偑側偄偺偱
愭掱偺偐偳傢偐偝傟偨娕斅偺応強傑偱栠偭偰杮摴傪偝傜偵恑傔偽
惃帄摪僩儞僱儖偑偁傝傑偡丅乧傕偟偐偟偰摶偭偰偙偺僩儞僱儖偺忋偺偙偲丠丠
偳偆偵傕抧恾偵梀偽傟偰偄傞傛偆側姶偠偱偟偨丅偱丄屻偱挷傋偰抦偭偨偺偱偡偑丄
偳偆傕栴報偱帵偝傟偨愭偼媽夛捗奨摴偺惃帄摪摶廻偩偭偨傛偆偱乧丅
屆偄奨暲偩偲巚偭偰尒偰偄偨偺偼丄幚偼峕屗帪戙偵夛捗偐傜偺嶲嬑岎戙偺
廻応偲偟偰塰偊偰偄偨偦偺挰暲傒偩偭偨傛偆偱乧丅傎偊傎偊乣(0丵0丅
抦偭偰峴偔偺偲抦傜側偄偱峴偔偺偲偱偼僄儔僀堘偄偱偡丅奆偝傫壓挷傋偼戝愗偱偡傛丅
偝偰偝偰丄偦偺傑傑崙摴俀俋係崋慄傪傂偨憱偭偰丄
師偵岦偐偭偨偺偼嶰戙丒暉椙丅PM俆丗侽侽丅
塅搒媨偱晧彎偟偰夛捗偱椕梴偟偰偄偨搚曽偝傫偑丄愴慄暅婣偟偨応強偱偡偹丅
搚曽偝傫偺愴応偱偺懚嵼偼戝偒偐偭偨傛偆偱丄
偍偍偄偵媽枊晎孯偺巑婥偑崅傑偭偨偲偄偄傑偡丅
偦偟偰偦偺杮恮偑晘偐傟偨応強偵杮恮愓旇偑偁傞偲偄偆偙偲偩偭偨偺偱偡偑丄丄丄
応強偑傢偐傫側偄偭(T仭T丅徻嵶側巎愓抧恾偑側偔偰丄
偳偙偵傕埬撪偲偐側偄偟乧丅寢嬊傢偐傜偢偠傑偄偩偭偨偺偱偡偑丄
偙偙傕乽傑偀偙偙傜傊傫乿偭偰偙偲偩偗報徾晅偗偰偒傑偟偨丅丅丅
 傑偨丄暉椙偵偼栰愴昦堾偑偁傝丄晧彎偟偨搰揷夽偝傫傕
傑偨丄暉椙偵偼栰愴昦堾偑偁傝丄晧彎偟偨搰揷夽偝傫傕
昦堾偱帯椕傪庴偗偨偲偄偄傑偡丅
壛偊偰怴慖慻偺廻幧偲偟偰偟傛偆偝傟偰偄偨偲揱傢傞
暉椙屼梡応愓傕偁偭偨偦偆側偺偱偡偑丄
暦偔偲偙傠丄嶐擭偺廫寧崰傑偱偼摉帪偺堚峔傪曐偭偰偄偨偲偄偆偺偵
庢傝夡偝傟偰偟傑偭偨傜偟偔丄尰懚偟偰偄側偄偲偺偙偲乧(侽仭0丅偑傃乕傫丅丅丅
搚曽偝傫偼屻偵暉椙偐傜挰庣壆偵堏偭偰丄孲嶳傊偺恑孯傪帋傒傑偡偑丄
媫绡擇杮徏墖岇偺偨傔挅昪戙忛壓丒曣惉摶傪栚巜偡偙偲偵側傝傑偡丅丅丅
偦偺挅昪戙忛傪椪傓傛偆偵暉椙偐傜挅昪戙屛傪嫴傫偱
斨掤嶳傪攓傫偱仺暉椙傪屻偵偟傑偟偨丅傑偨傕傗塉偵尒晳傢傟昁巰偺堏摦偱偡乮媰
PM俆丗係侽丅擔曢傟傕娫嬤偲側偭偰偒偨偺偱丄彮乆傾僋僙儖傪傆偐偣偮偮
嶳摴傪媫偓傑偡丅丅丅柀挰偱偺暘婒偱導摴俁俈係崋慄偵撍偭崬傒丄
晝忋偵偼恀寱偵婃挘偭偰傕傜偄傑偟偨丅
壗屘偭偰丄丄丄偲偵偐偔僿傾僺儞僇乕僽偺楢懕偱丄偡偭偛偔嶳摴傜偟偄嶳摴丅
嫹偄偼尒捠偟偼埆偄偼偱乧丅愘幰傕慜曽妋擣昁巰偱偟偨乮旀丅
偟偐傕晐偄偙偲偵丄偙偺導摴俁俈係崋慄偼搤婫偼摴楬晻嵔偡傞傛偆側
応強傜偟偔丄丄丄屻懕幵傕偄側偔偰惁偔怱嵶偄応強偱偟偨傛乮媰丅
 偲偄偆傢偗偱丄恊巕懙偭偰傑偨偟偰傕價價儕側偑傜昁巰偺嶳墇偊傪壥偨偟偰
偲偄偆傢偗偱丄恊巕懙偭偰傑偨偟偰傕價價儕側偑傜昁巰偺嶳墇偊傪壥偨偟偰
敳偗弌偨愭偼徏暯壠楈昣偺榚丅傕偆擔曢傟傑偱偁偲俁侽暘傕側偄偩傠偆偲丄
媫偄偱導摴俁俀俆崋慄増偄偺挀幵応偵幵傪掆傔偰丄偄偞梕曐條偺偍曟嶲傝丅
PM俇丗俀俆丅楈昣偺擖傝岥偵懕偔榚摴庤慜偵乽傑偪偵楌巎偁傝乿偲偄偆
梕曐條偺幨恀擖偱戝偒側娕斅偑偁傞偺偱丄擖傝岥傊偺摴偼偡偖偵傢偐傝傑偡丅
偑丄擖傝岥偐傜愭偼斀懃偱偡丅丅丅嶲攓幰傪嫅愨偟偰偄傞偐偺傛偆側嶳摴(T仭T丅
恊巕懙偭偰傂乣傂乣尵偄側偑傜丄傕偆娋偩偔偩偔偱忋傝傑偟偨丅
傛傝偵傛偭偰梕曐條偭偨傜堦斣忋偺堦斣墱偵偄傜偭偟傖傞傕偺偩偐傜丄
擇搙傎偳摴偵柪偄側偑傜丄傗偭偲偺偙偲偱扝傝拝偗傑偟偨丅丅丅
偑丄偦偙偱寎偊偰偔傟偨偺偼恖夰偭偙偄埜丒埜丒傾僽両両偆偓傖乗乗乗乗偭両両
 偙偭偪偔傫側乗乗乗偭嚁(邅∵)丼(邅∵)丼偲傾僽傪暐偄側偑傜梕曐條偺偍曟嶲傝丅
偙偭偪偔傫側乗乗乗偭嚁(邅∵)丼(邅∵)丼偲傾僽傪暐偄側偑傜梕曐條偺偍曟嶲傝丅
棊偪拝偒偺側偄恊巕偱偡偄傑偣傫偱偟偨丅偼丄抪偐偟偄丅丅丅
偟偐傕庤傪崌傢偣偰偄傞偆偪偵傒傞傒傞埫偔側偭偰偒偰丄偙傟偼僿僞偟偨傜
楈昣偱憳擄偡傞偐傕乧偭偰丄偦傟偩偗偼屼姩曎偭乮媰乯偲丄媫偄偱嶳摴傪壓傝傑偟偨丅
栠傝摴丄楌戙夛捗斔庡偺曟傪攓傒側偑傜埫偄嶳摴傪壓傝偨偺偱偡偑丄
楌戙斔庡偺偍曟偼偲偰傕戝偒偔偰棫攈側傕偺偱丄
摉帪尃埿傪屩偭偨偦偺徾挜偺傛偆偱偟偨丅偑丄偦傟偲斾傋偰
梕曐條偺偍曟偑偄偐偵傕幙慺偱偲偰傕庘偟偔巚偄傑偟偨丅丅丅
偳偆偟偰傕棊擔偺攚宨偑忴偟弌偝傟偰偄傞傛偆偱丄丄丄傗傞偣側偄偱偡偹丅
偦傫側傢偗偱屻傠傪怳傝岦偔偺傕晐偄偔傜偄恀偭埫偵側偭偰偐傜
柍帠楈昣傪敳偗弌傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅晝忋堦弿偵棃偰偔傟偰偁傝偑偲偆丅
愨懳堦恖偩偭偨傜搑拞偱堷偒曉偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅丅丅
PM俈丗侽侽丅偙傟偵偰杮擔偺弰嶡偼廔椆丅
杮擔偺屼廻偼拞挰僌儔儞僪儂僥儖丅
崙摴侾侾俉崋慄偲夛捗庒徏巗栶強慜偺摴偑岎嵎偡傞嬤偔偵偁傞價僕僱僗儂僥儖偱偡偑丄
偙傟傑偨偙偺擔偼偦偺摴乆偱屼嵳偑偁傞偲偄偆偙偲偱摴楬晻嵔偵偮偐傑傝丄丄丄
傢偐傜側偄摴傪偖傞偖傞夞偭偰傗偭偲偺偙偲偱廻偵擖傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偲傎傎乣丅
偟偐偟丄偙偙偱夛捗庒徏巗撪偺抧恾傗妱堷寯摍丄怓乆擖庤偡傞偙偲偑弌棃傑偟偨v
偦傟偵婐偟偄偙偲偵愒儀僐偺僗僩儔僢僾傪僾儗僛儞僩偱捀偒丄
壛偊偰屼晽楥偵偼僶僗僉儏乕僽傑偱梡堄偝傟偰偰vvv
儐僯僢僩僶僗偱偡偑備偭偔傝擖梺偱偒傑偟偨(^乗^)偁乣傃偽傃偽侓
堦擔栚傪柍帠偵夁偛偣偨偙偲傪姶幱偟偮偮丄柧擔偵旛偊偰憗傔偵廇怮丅
擇擔栚偼挬堦偐傜娵乆堦擔夛捗巗拞偺嶶嶔偱偡両
2004.8.8 佀丂丂 |
|