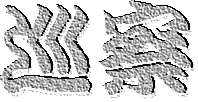
2009.01.17
■水仙と明治陸軍要塞 : 灘黒岩水仙郷、洲本立川水仙郷→ 生石山砲台跡、由良要塞跡
▼ 2009.01.17       |
間 |
朝食がお雑煮続きで、 まだお正月気分な一月半ば。 天気は良く、日向が温かい今日は ちょっと足を延ばして淡路島へ。 前々からTVで紹介される度に 行ってみたいと思っていたところ、 家族の休みが揃ったので 灘黒岩水仙郷へ車で早速GO! 残念ながら一連のETCの波に乗り遅れ、 軒並み売り切れ状態で我が家の車には 未だETC搭載できておらず、、、 一般車両でブイブイ! まずは明石海峡大橋を観賞。 雲一つない快晴の空の下、 青い海との間に白い綺麗な曲線。 冷えて清んだ空気が映えさせていました。 そしてカーナビを頼りに進んでいたところ、 陵墓らしきものを見つけたので ちょっと立ち寄ってみることに。 第47代淳仁(じゅんにん)天皇淡路陵。 淳仁天皇は崇徳天皇と同じく、 本州から流された廃帝で、 淡路公とも称されて、「淳仁天皇」の諡号は 明治政府によって追贈されたそうです。 なんかひっかかると思っていたら、 高橋克彦著『風の陣』の影響でした。 確か天命篇あたりだったはず…。 淳仁天皇を廃した孝謙上皇が帝位に返り咲いたその裏で、 女帝を誑かし、陰で政治を操る怪僧・弓削道鏡が、、、 といったところでしたでしょうか。 内裏のスキャンダルって面白いね。(あ、物語の中でね。 それに振り回され立ち向かう嶋足や天鈴様←ファンv 奇計妙策が面白かったから覚えてた(笑 さて、脱線してしまいましたが、 お昼過ぎに国立公園淡路島、灘黒岩水仙郷に到着v この日も沢山の観光客で賑わっていて、 すっごく手前の広間に駐車場が設けられていて そこからシャトルバスで水仙郷へ。 海に面した急な斜面一面に水仙の花が満開!! すべての花が海に向かって咲いている為、 海側の斜面に設けられた葛折りの細道から振り返ると 黄色と白の明るい花弁が太陽に照らされて眩しい!! 匂い立つように海風に戦ぎながら凛と咲く水仙。 花々に囲まれてお登勢という女性像がありました。 説明書きによると、 淡路島灘黒岩は船山文学長編歴史ロマン『お登勢』の 生誕の地ということで、 幕末維新の時代、貧農の娘お登勢が 奉公にあがっていた稲田家分藩騒動が原因で 北海道静内へ移住し、開拓に従事するようになって 愛を貫き、修羅場をくぐり、大地に生きる 芯の強さをもった女性として紹介されてありました。 興味ある時代なだけに、読んだことないし せっかくの機会だと思ったので後日、船山文学 早速図書館で蔵書検索したんですが、、、 これって人の名前じゃなかったんですね。 船山馨著で『お登勢』見つけました(とほー。 |
||
  | 間 |
さてさて、灘黒岩の水仙を観賞して水仙に魅せられて 水仙の植木鉢をお土産に買ったり、 アイスを食べたり焼き芋を食べたりして お腹も満たされたところで、お店の人に もう一か所、近くで水仙郷があると教えられたので 行ってみることに。 シャトルバスで一度駐車場へ引き返し、 灘黒岩より車で今度は山道を走ること数分。 瀬戸内海国立公園、洲本立川水仙郷へ。 なぞのパラダイスってぇ怪しげなものもありましたが、 そこはスルーして、、、 谷間一面に咲く白い水仙がとっても可憐v 灘黒岩は海に面して潮風があるものの 日向で温かかったのですが、 こちらは谷間の日陰で山から吹き下ろす冷たい風が 寒いのなんのっっっ><。 この白い水仙、欧州で水仙といえばこの花なんだそうで。 ギリシャ神話に出てくるのもこの白い水仙なんだそうです。 ほかにも八重咲きのものや、全部黄色い水仙もあり 寒さに震えながらも楽しませてもらいました。 |
||
     |
間 |
と、主目的を達したところで、 ちょいと時間が余ったので家族を巻き込んで 趣味の寄り道をば(笑 カーナビで見つけた砲台跡の情報。 前調べしていたわけではないので、いつの時代の どんなものがあるのか分からなかったのですが、 海岸に据えられて残っている砲台といえば、 幕末・明治・太平洋戦争、なんでもござれだったので とりあえず行ってみることに! 行ってびっくり。 舗装されてないし、山道だし、崩落しかけてるし。 けど雰囲気は抜群! レンガ積みの建築物からみるに 明治期のものとみた。 どうやら公園として整備中のようで、 工事車両が数台停まっていたので 近くの広間に駐車して降りてみることに。 偶然、同じ趣味であろう方がカメラ片手に ズンズン山道を入って行かれたので我らも続いてみた。 で、説明書きを見つけました! 生石山砲台跡、由良要塞跡。 幕末、海防の備えに幕府の命で造られた砲台場で、 谷間の向うに海を隔てて見える成ケ島に置かれた 巨大な高崎砲台を中心として砲台場群が築かれて 紀淡海峡に睨みをきかせていたのだそうです。 明治時代になって由良は海防上、東京湾要塞に次ぐ要所 と位置づけられて紀淡海峡・鳴門海峡の 防衛拠点として由良要塞指令部が置かれました。 で、その高崎砲台などに据えられた 二十八センチ榴弾砲が日露戦争の際、 二百三高地に運ばれて利用されたという 逸話が残っているのだそうです。 ちょうど司馬遼太郎著『坂の上の雲』読んだところで 胴が震えました><。 こんなところで関連史跡に立ち寄ろうとはっ。 山頂近くに今も残るのレンガ造りの遺構は規模も大きく 砲台跡には砲身も展示されてあり、 当時を偲ばせる空気がそこにありました。 このまま後世に歴史遺産として保存されるとよいですね。 最後に強烈なインパクトを受けて 今日の小旅行も大満足! |
2009.01.17