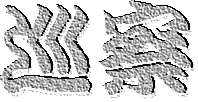
2008.08.12
■神話+西南戦争を巡る(2) : 延岡→ 高千穂→ 八代→ 日奈久→ 人吉
▼ 2008.08.12              |
間 |
昨日も大概でしたが、本日もめっちゃ旅程テンコ盛りなんで AM6:00起床、そのままホテルをチェックアウトして 朝靄の立ち込める中、早速史跡めぐり開始です! 国道10号線(日向街道)をまた北に向って 車を走らせること20分。 最初に向かった先は西郷茶屋ドライブイン。 西南の役時、延岡まで逃れてきた西郷さんは、 日向街道と並行して流れている北川を小舟で遡り、 平成十年八月十二日に、この地に上陸したのだそうです。 この日向街道をさらに北上すれば、 八月十三日以降の西郷さんの宿陣の地など(吉祥寺ほか)が あるそうなのですが、時間も限られているので この付近にポイントを絞ることに。 まずは近くに薩軍野戦病院が敷かれたという 成就寺を探して国道10号線をを改めて北上…、、、しすぎ、 気づけば日向内駅を通り越してしまい、 慌てて西郷茶屋までUターン。 雨がパラついてきた中、大凡の場所を記した自前の地図を手に、 「あれ〜??この近くって聞いてたんだけど…何処??」と 今度は徒歩で散策したところ、見つけました〜><。 分かりにくい、、、っていうか道から見えてなかった! 国道10号線と並行して線路があるのですが、 それが道路より高い位置にあり、バス停「可愛」の後ろに その線路に続くちょっとした登り道があります。 踏切のない所を線路向こうに渡れば、 大きな銀杏の木に隠れて成就寺がありました。 AM7:10、お寺の朝は早く、門が開いてて良かったです。 人の気配はないものの、早速「おはようございまーす」と、 お邪魔して、お参りして見学させて頂きました。 延岡陥落を前に激戦が繰り広げられ、 多くの死傷者がここに収容されました。 案内板によると、敷地の南東部には 当時の墓石が今もあるということです。 お寺を後にして、また線路を跨いで左右を確認。 電車が来る気配がまるでしないので、 線路のど真ん中で記念撮影。一人で。 …なんか線路を歩くのって楽しいですよね?←拙者だけ? 「廃線なのかな?」と思って線路の高い位置から 周辺の景色を撮影して車に戻ったのですが、 そしたら電車が来たー@▼@;いやー、危なかったです。 さて、元来た道を少し戻り、俵野へAM7:20、 児玉熊四郎方・西郷隆盛宿陣跡を訪ねました。 道沿いに西郷さんの道案内の看板があり、 指さす方へ。。。こっちでごわすか? 西南の役最初にして最後の全部隊での一大決戦であった 和田越の戦いに敗れた後、官軍の包囲網を突破する 薩軍決死の可愛岳突囲が決断された地です。 現在、資料館になっているということだったので 楽しみにしていたのですが、、、 開館時間を失念していました><。今7時て…。OUCH! そんなわけで、西郷さんが陸軍大将の軍服等を焼いただとか、 愛犬を放して別れを告げただとか、色々エピソードが残る地を シャッター越しに眺めてきました。よよよ。 左手の岡上には「明治十年激戦地」の立派な碑がありました。 この後、広く周辺をウロウロしてみたのですが、 西郷さんの長男菊次郎君が療養した児玉惣四郎方だとか 桐野利秋宿営の地・岡田忠平方だとか 可愛岳登山口だとか、飫肥隊小倉処平自刃の地だとか、、、 下調べが足らず場所がわからず見つかりませんでした。残念。 仕方なく、国道10号線を南下して戻り、いざ和田山峠へ! これがまた車で行けるの??って感じだったんですが、 和田越の交差点を折り返し、対向車がないことを祈りつつ 特養の前の細い道(旧国道10号線)をのぼって行きました。 AM7:45。子供の握り拳程ある大きな沢蟹がいっぱい! 山頂は車二台がすれ違えるくらいの広さがあり、 そこに「和田越決戦之地」の大きな碑と案内板がありました。 西郷さんが開戦以来唯一指揮を執った場所です。 明治十年八月十五日晴天、午前九時頃の砲声に始まり、 中央の和田峠・堂坂方面に展開した別働第二旅団は 堂坂のぬかるみと薩軍の砲撃に苦しみ、 そこに桐野利秋率いる決死精鋭の一隊が攻撃した為、 別働第二旅団は危機に陥りました><; しかし!そこに第四旅団が進出して別働第二旅団を救援。 その後両旅団と薩軍は一進一退となるも、 真夏の灼熱地獄の中、午前十一時頃薩軍の一角より破れ、 死闘五時間、午後二時頃薩軍は全軍敗走し、 俵野に至ったといいます。 奇しくも同じ真夏の太陽の下、当時の場景を想像。 炎天下の中での戦いなんて、、、 鉄砲の他に熱射病で倒れた人も沢山いたと思います><。 滲む汗を拭いながら写真を撮ったり案内板を読んでいると いきなり土砂降りの雨! あまりにも突然だったので、たぶん通り雨なのだろうと 車中で雨宿りがてら朝食。 宮崎限定パン(←限定物に弱い)などで腹を満たしていると、 雨につられてか、道にまでワンサカ湧いて出てきた 沢蟹の群れにビックリ。。。うじゃうじゃ…O_O; 10分もすると、蟹の大行進も雨も治まってきたので 来た道を引き返すことに。 地図で見たところ、この旧国道10号線は直進しても 先は国道10号線に続くようなのですが、 どう見ても細い山道な上に、雨が降った後で 最悪斜面が崩れてそうな気がしたので直進は避けました。 んが、ここで車の向きを変えるのに切り返すこと11回><; 拙者の運転技術では20回やっても無理サ。父上ありがとう! 戻り道、雲が晴れてきたところで、開けた場所から 麓と樫山の方向を目視で確認。 嗚呼〜っ(興奮!)ここらへんに別働第二旅団が配置されて、 あっちで山県さんが指揮してたってわけです!! 地図で見てもわかりますが、直線距離にして1km程度。 両軍の将が目視できるような凄く近い場所にいたんですね!! というわけで、AM8:05、 次に向かった先は樫山の山県有朋中将陣頭指揮の地。 和田越の交差点を南西へ、 樫山町の交差点の北側の一角に案内板があります。 雨は上がったものの短時間に酷く降ったので路面は水浸し。 岡上には上らなかったのですが、 神社横からは登り口があるようです。 ここから逆に和田峠を見てみたかったのですが、 足元が悪そうだったので断念しました。 |
||
                  | 間 |
そのまま南下して昨日から往ったり来たり 何度目かの五ヶ瀬川を渡り、 AM8:35、城山公園に立ち寄りました。 慶長八年(1603年)、初代藩主高橋元種が築いた 延岡城の跡地を整備した公園ということで、 駐車場完備なのですが、、、 ここも残念ながら開園前で駐車場に停めれず…+▼+; 他にも数台観光客の車が来ていたのですが、 皆さんは渋々引き返される中、 拙者達は仕方なしにガンガン上まで車で上ってきました! 別名、県(あがた)城、亀井城ともいわれる平山城です。 「あがた」というのは、「吾田」「英田」とも書くようで、 古く奈良時代頃に延岡地方がそう呼ばれていたそうです。 で、その延岡城で有名なのが千人殺しの石垣! 二の丸跡から見上げる高さ22mの本丸高石垣。 礎石を一つ外すと石垣が崩れて千人を殺せるのだとか。 時間が惜しく、本丸まで上らなかったのですが 立派な石垣があるのに天守閣がないのが残念ですね><。 空模様を気にしながら、 大瀬川沿いに車を西に転がし、 AM8:45、次に訪ねたのは 大内善吉家跡・西郷隆盛宿陣跡。 こちらには先ほど訪ねてきた西郷茶屋へ向かう前に 西郷さんが八泊宿陣した場所だったそうです。 大瀬川対岸に渡り、AM8:55、 次に訪ねましたのは 中城家・山田顕義少将宿営の跡。 時間軸は前後しますが、 西郷さんが大内善吉家を出てから 四日後の明治十年八月十四日、 当地に山田顕義少将が宿陣。 今もお住まいのようなのですが、 時間が時間なだけに、アポも取っていなかったので お訪ねするのも気が引けて、 外側からそっと窺わせて頂きました。 ここで作戦を考えたり指揮を執られていたわけですね。 川岸から和田峠の方を臨むと、雨に洗われて 鮮やかな風景を楽しむことができました。 気持ちいいー><v 気分を少し変えて、次に向かう先は神話の里。 国道218号線へ入り、 西へひたすら山道を走ります。 神話街道を快走してAM9:50。 まずは観賞、青雲橋。 ここに来るまでにも 何度も巨大なアーチ橋がありましたが 青雲橋は国道に架かるアーチ橋で 東洋一なのだとか。 水面からの高さ137m、長さ410m。 道の駅青雲橋の公園より全容を楽しめますv さらに先へ、馬門のT字路より県道7号線を北上し、 AM10:35、天岩戸神社・西本宮。 皇祖神・天照大神を祀る、厳かな雰囲気漂う場所です。 拙者も一時期神話に嵌って色々調べたこともありましたが、 すっかり忘れていたので(^^; 他のツアー客に紛れて入宮前に一緒に清めてもらったり ガイドさんの説明を盗み聞きしながらお参りさせて頂きました。 そこで面白いものをいくつか発見。 招霊(おがたま)の木。 神前に供え神霊を迎えるための木ということで、 榊の木の前身なのだとか。 そして神楽殿の飾り。 皆気付かずスルーしちゃってたんですが、 神楽殿を覗きこむと天井を飾った紙に 不思議な細かい細工がされてあり、 賑やかで、まじないのような感じでした。 後で調べたところ、この飾りは「えりもの」というものだそうです。 神楽を舞う神庭(こうにわ)は神聖な場所で 東西南北に仕切られており、東には木徳人、 西に土徳人、南に火徳人、北に金徳人がいるとされ、 それぞれに「木」「土」「火」「金」の印が 透かし彫りされてありました。 そんな人工的なものもあれば、 苔むした石燈篭に木の芽が息吹いていたりなど、 自然的なところにも神秘さを感じたり、 ちょっと浮世離れした空間でした。 そしてそして、さらに不思議で違和感を覚える場所へ。 御存知、天照大神が弟の乱暴っぷりに立腹して 岩屋の奥で不貞寝したことで有名な天岩戸のお話しの舞台。 岩屋の洞窟がある岩戸川の対岸中腹は 立入禁止の神域なのですが、 その手前、天岩戸神社の裏参道を進んで、 八百万の神々を祀る天安河原に行ってきました。 岩屋に隠れた天照に出てきてもらうために 他の神々が作戦を練った場所です。 因みに、その作戦で岩屋前で宴会をして、 天鈿女命(あめのうずめのみこと)が持って踊ったのが 招霊の木の枝だそうで、鈴のような形の実がなるそうです。 渓谷は川の水しぶきが煙っているのか マイナスイオンが充満v 遊歩道を下りながら、森林浴も気持ちいい 素敵な場所だと思っていたのですが、 AM11:00、天安河原に出て気分が変わりました。 直感で「人間が居ていい場所じゃない」と思いました。 神々が祀られているというか…、 まるで三途の川、賽の河原を見るようで><。 というのも、ここで沢山の石を積み重ねて祈願すると 願い事がかなうという信仰の慣習があるということで、 ここら一帯の小石はすべて積み重ねられてあり、 一つで転がってる小石なんてないんです。 まさに「一つ積んでは父の為、二つ積んでは母の為…」 な情景に背中が冷たくなる思いでした。ぞぞぞ。 他にも観光客の人達がいるから居れるような場所で、 絶対一人じゃ怖くて来れない場所です><。←怖がり。 神域ってそんなもんですよね。 お参りして父上も長居したくなかったようで、 そそくさと退散。 そんな帰路、石橋の手前で背後に蛇が出てきて、 蛇嫌いな拙者達親子が 「蛇!?蛇が居るって!!蛇っ!蛇っっ!!」 と叫びながら走りだしたのにつられて、 他の観光客の皆さんもギャーギャー大騒ぎになりました(笑 そんな珍騒動に薄気味悪さも振り払えたので、 天岩戸神社・東本宮にも行ってみることに。 AM11:25。人っ子一人いやしねぇ…。 なんで!?西本宮には沢山観光客の人達いたのに。。。 父も車中から出たがらず、一人で参道を登ることに。 が、雰囲気に呑まれて、またしても背中がゾクゾクしてきたので 途中で引き返すことに><。←だから怖がりなんですってば。 数珠は常備ですが、やはり神様に仏様の力は及ばないようです。 気を取り直して櫛觸(くしふる)神社へ。AM11:45。 祀神は天児屋根命(あめのこやねのみこと)、 天津彦々火瓊々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)らで、 古来より武神としての信仰が厚く、 高千穂を代表する聖地の一つなのですが、 こっちも人っ子一人いやしねぇ…。なんで!?どうして!? マイナー!?マイナーなの!? またしても父は車中から出たがらず、 一人で参道を登ることに。 うす曇りの中、生い茂る木々の間は真っ暗闇。 途中社務所に灯りがついていたので、 それを目指して辿り着くも、何度呼んでも誰も出てこず…。 さらに奥の石段の先には本殿が薄らぼんやり見えたので もう登るのは断念して石段下からお参りして引き返しました。 ←だから…以下略。 ここには瓊々杵尊が高天原よりこの地に 天真名井(あまのまない)の水を移した御神水があったり、 春の高千穂神社、秋の櫛觸神社例祭で お神楽が奉納されるなど見所ある神社ですよ〜。 晴れてたら人は来るのかな〜? 誰もいない神社なんて怖いことこの上ないですよ〜><。 というわけで、次も誰も居なかったらどうしよう…と 思いながら、高千穂神社へ。AM12:00。 よかった、、、こっちは沢山人がいましたよ〜><v とうとう小雨が降ってきた中、傘をさして参拝。 高千穂郷の中で格式高い「高千穂八十八社」の総社。 境内には、鎌倉将軍源頼朝の命で 秩父の畠山重忠が代参して植樹した秩父杉や、 夫婦杉という根元が一つになっている二本の杉があります。 「如何なる事があっても別れられない」という形なことから、 夫婦杉の廻りを手をつないで3回廻ると 夫婦、友人、相睦まじく、家内安全、子孫繁栄の 三つの願いが叶うのだとか。 また、案内板によると源頼朝が寄進したという 鉄製の狛犬があるというので、 階段下の狛犬がそうなのかな?と思って見てきたのですが、 これはどう見ても鎌倉期の鉄ではない。。。 でもこの狛犬は子供を抱えているのが面白い。 狛犬を詳しく調べたことないですが、こんなの初めて見たかも。 そして後で調べてみたところ、 やはり源頼朝が寄進したという狛犬は別物でした。 どうやら本殿の中に安置されてあるようで。 人混みに流されて拝見しそびれました〜っ残念。 さて、また雨も上がったところで神社を後に 次は高千穂峡へ! 今日は天気まで忙しないですね。 すぐにカッと太陽が照りつけるようになり、 雨上がりに蒸し暑さ急上昇TωT; 流石にこちらはシーズンの為、 駐車場がのきなみ満車><! 駐車場よりシャトルバスにて 山道をうねうね移動すること約10分。 AM12:55、やっとこさ渓谷に到着v 国の名勝天然記念物なだけあります! 一目で魅了されましたv どうやってこんな渓谷になったんでしょうね。 説明書きによると、阿蘇山の噴火で噴出した溶岩が 五ヶ瀬川に沿って流れ出て、空隙に冷却された為に V字型に割れてできた渓谷なのだそうです。 滝壺には手漕ぎボートを浮かべてこの渓谷を 下から仰ぎ見て楽しむこともできるようなのですが、 シーズン時は予約が必要なのだとか。 すでに何艘も浮かんでて一層谷間が狭くなってました(笑 そして日本の滝百選に選ばれている真名井の滝の周りは 水しぶきがひんやり気持ちよかったですv |
||
             |
間 |
さぁ!気分をまた戻して国道218号線の先を進みます。 時間に余裕があれば途中さらに寄り道して 西郷さんが退軍路として使用したという飯干峠にも 足を延ばしてみたかったのですが、 目標午後3時に八代入りだったので、 カーナビの到着予定時間と相談して断念。。。 途中、睡眠休憩をとって、とにかくひたすら西へ! PM3:50、なんとか鏡内橋にたどり着けました><; 鏡町鏡の交差点を西に入ったところにある小さな石橋です。 はい、また時間軸を戻しますが、 西南の役で熊本戦の際に、北上する背衝軍の斥候と 熊本城攻めの薩軍から南に派遣された斥候が 初めて出会った場所です。 案内板を確認したところ、 ここは八代から松橋の下住還の要所だった為、 高札場としても使われていたということですが、 よくまぁ斥候同士がカチ会ったものですね。 さて、そのまま背衝軍関係の史跡を巡ります。 別二が本陣とした光徳寺にまず向かったのですが、 対面の細道に入れずあえなくスルー><。 仕方なく、慈恩寺の方へ。PM4:30。 明治十年三月十九日、日奈久・洲口に上陸し、 各地で薩軍を撃破して八代に進出した 別二と別三の両旅団が本営とした場所です。 これまたお寺の屋根は見えているのに 正門に面している路がわからず、地元の奥さんに路を尋ねて 大通りに停車して父を残し、徒歩で訪ねました。 が、ちゃんと東面の路地に駐車場ありました(とほー。 ←奥さんには夫婦だと勘違いされるし…二重でとほほー。 別二は山田顕義少将、警視庁巡査(警視隊)で編成された 別三は川路利良少将が率いていましたが、 彼らの衝背軍が八代を占領したことで 熊本戦の薩軍敗北を決定付けました。 しかし、この衝背軍が上陸する一日前に熊本戦に際して 先に投入されていた警視九州増援部隊で 豊後口警視隊として戦っていた佐川官兵衛さんが 阿蘇二重峠で戦死しています。 この後、山川浩中佐が熊本城目指して突入していきますが、 佐川官兵衛さんの訃報はどこで知らされたのでしょうか。 例の熊本城連絡の抜け駆けに立腹した山田少将は 山川中佐をわざわざ川尻の本営まで呼び戻して 激しく面罵したそうですが、、、 この時に聞かされていたら耐えられないっ浩><; とか、グルグル想像しながら、PM4:45、 お寺を後にして市営駐車場に駐車して八代城跡へ。 加藤清正の子忠広が築城した八代城。別名、松江城。 お城の遺構は石垣のみで、城跡には八代宮があります。 お宮さんにお参りしてから、 石垣に上ってお堀を覗きこんできました。 まぁなんとオープンな。柵がない。 一歩間違えばドボン…という、結構なスリルです。 天守台の方まで半周程度歩いたのですが結構な広さ。 石垣も素晴らしいものですが、当時は一国一城令のもと 熊本藩内に熊本城と並んで何故建てられたのか。 ←薩摩藩絵の備えだとかキリシタン弾圧への備えだとか。 さて、改めて国道3号線を西へ車を転がし萩原堤へ。 萩原町の交差点付近、球磨川が大きくカーブするあたりで、 官軍と薩軍の激戦地の一つ。 司馬遼太郎揮毫による記念碑が 大きな銀杏の木の近くにあります。 PM5:10、宮崎八郎戦没碑。 宮崎八郎は熊本協同隊の参謀長として薩軍と共に戦い、 衝背軍に占領された八代を奪還すべく、伝令として走り 辺見十郎太らと合流して官軍を山間で蹴散らすも、 この萩原堤で銃弾を受けて戦死したということです。 八代市教育委員会文化課の担当者さんに伺ったところ、 戦死地については諸説あるそうで、 もっと上流のガードレールの脇にも標木があるそうです。 倒れ掛かっているということだったのですが、、、 川沿いに遡ってみたものの見つけられませんでした。 ←もう少し内陸部の桑畑だったと聞いていると話す 地元の年配の方もいらっしゃるそうで。 しかも残念ながら、 ここで雨がパラパラと降り始め、 太陽もそろそろ傾いてきたので、 ここから一気に捲き入ります! ラストスパート! さらに西に車を進めて、次に 妙見町の八代神社へ。PM5:20。 当時は宮路村といって、 ここでも激戦が繰り広げられたそうで。 境内の大楠に西南戦争時の弾痕が多数、、、 遺蹟案内板によると、 境内の樹木が台風で倒れたので製材に出したところ 銃弾が入っていて鋸の歯がつぶれてしまったとか。 今も立つ大楠の幹の中にも 沢山の銃弾が撃ち込まれてあると思うと 痛々しい限りです。 大切な歴史の生き証人、 これからも永く生きて欲しいですね。 続いて、南へ細い道を 対向車が来ないことを祈りながら進み 宗覚寺へ。PM5:30。 薩軍の本陣が置かれたということで、 ここも激戦地となり その際に本堂と庫裏が焼失してしまったそうです。 薩軍が撤退する時に無念から斬り付けた刀傷が 山門の柱にあるというので見てきました。 右にも左にも…うぅ、痛々しい。 因みにこちらのお寺は加藤清正の嫡男 忠正の菩提寺ということで案内がありました。 慶長十二年正月に江戸屋敷で疱瘡で亡くなった為、 古来忠正の墓は疱瘡の神として信仰されたとか。 墓石は削られてなさそうでしたよ^^;ほ。 で。 近くの春光寺にも弾痕の跡だとか 西南役戦死者之碑があるというので 桜馬場戦場跡にも立ち寄ろうかとも 思ったのですが、、、 道が細いわ日没までカウントダウン始まったわでパスして 本日の〆、官軍上陸之地を目指して一路、日奈久へ! 国道3号線をひたすら南下し、 途中、交通事故による下手な交通整理で じりじり足止めされるも、、、(汗っ ←現場近くだけでなく数キロ手前から 迂回路確保しなきゃダメですね。 なんとか日没までにたどり着けました。PM6:05。 日奈久上西町交差点を右折した所に 立派な石碑がありました。 解説によると、 この周辺は薩軍の糧食基地だったところで 日奈久南方洲口に官軍数百が上陸し、 その援護に艦砲射撃をして この地を占領し衝背軍の上陸地となったとのこと。 その際の銃弾跡が海岸に面していた 八代屋の柱に残っているそうです。 港には小船が沢山碇泊していて、 日没前のキラキラした海が綺麗でしたv これにて本日のミッション終了><。頑張った! が、本日のお宿は人吉なので 九州自動車道をもうひとっ走り。 不毛なことに日奈久ICからは人吉方面に入れず、 来た国道3号線を北へ戻り八代ICから改めて南下。。。 トンネルばっかりで山の多さに驚きながら、 当時はこれを徒歩で移動していたんだ…と感心しきり。 途中、肥後トンネル6Kmなるものもありました(長っ。 山江SAで夕食に熊本ラーメンを食し、 PM8:00、無事ホテルサン人吉にチェックイン。 早朝からの突貫移動も無事にこなせて父上に感謝。 明日も強行軍なのでヨロシク頼みます!ぇ。 |
2008.08.12