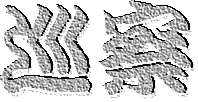
■佐賀の役+西南戦争(1) : 大分→ 太宰府→ 佐賀→ 武雄
夏だ!海だ!九州だ!!祝!九州初上陸!!
今回のコンセプトは佐賀の役、西南の役を巡る旅なのですが、
思いついて準備し始めたのが一ヶ月前なだけに、
知識は付け焼刃ですし、ベースは『獅子の棲む国』です。あはっ☆
もう何がどうとか言う前に、行きたいと持った場所に足を向けます!
そして、この旅行の為に佐賀の乱については「青梅」の三太さんと、
西南の役については「きららとんぼのたからばこ」のきららとんぼさんに
大変お力添え頂きました。資料提供ありがとうございます!!
そんなわけで全行程は車移動で、九州上陸後の全行程は以下の通り。
大宰府→ 佐賀→ 長崎→ 島原→ 熊本→ 阿蘇→ 湯布院→ 別府→ 大分 と、
走りも走って865.3km。
長い行程な上に今回も見所満載ですので気合入れて行きます!
湯治も兼ねて今年もお供は父上です。
三年連続、夏休み親子旅行だよ(^―^(^―^)
 12日、正午。ちょうど盆時期でどこも大渋滞だったので早めの出発。
12日、正午。ちょうど盆時期でどこも大渋滞だったので早めの出発。
今回利用するのは『ダイヤモンドフェリー』。大分入港のフェリーです。
PM3:45、神戸六甲フェリー乗り場到着。
カーナビの渋滞情報を頼りに抜け道を走るも大渋滞に巻き込まれ(泣
幸先の悪さに眉根を寄せながら乗船手続き。
出航はPM5:50だったのですが、
二時間前から続々と車が並びだしたので早めに到着して良かったです。
予約してても早めに並んだ方が早く乗船できるのでいいですよv
席取りは早い者順ですからね!
 言わずもがなパンピーですので二等室です。雑魚寝も初体験(笑
言わずもがなパンピーですので二等室です。雑魚寝も初体験(笑
盆時期は満席で全席指定だったので、
最初は大人しく船室で陣取っていたのですが、
「ボッボッボッボッボッボッボ…」とエンジンの振動に
とても横になっていられるような状態ではなかったので、
出航を見にいこうと甲板にあがりました。
夕日の中の出航で物悲しいような感じがしましたが、
PM7:00、明石大橋の下を潜り抜けました。
上は何度も通りましたが、下から橋を仰ぎ見るなんて初めてv
まだ夕日の薄明かりに照らされた橋の光景が綺麗でしたよv
 PM7:30、レストラン…というか食堂で夕食。
PM7:30、レストラン…というか食堂で夕食。
微妙に左右へ傾く席に違和感を覚えながらもバイキング料理完食。
乗船前から念のために酔い止め薬を飲んでいて良かったです。
食事後も甲板に上がっていたのですが、
明かりがなく、真っ暗な海が怖いなと思っていると
PM8:30、雲の切れ間から星を臨むことが出来ましたv
周りがいっさい闇だったので星が明るく見えました。
しかしながら、やることもなく、PM9:00。早っ!(゚▲゚;
明日は早いこともあり早々に消灯。
「絶対、無理。絶対、寝れない。」と思っていたエンジン音も
疲れた体には関係ありませんでした。熟睡(笑
が、幅が畳三3分の2程度しかない狭さは窮屈でしたよ。。。
気が付けば明けて13日、AM5:00起床。早っ!(゚▲゚;
出航前には「竜馬さん気分が味わえるかも♪」とか思ってたけど
そんな余裕なかったです。船に乗れたことだけで胸一杯でした(笑
AM6:00、大分港に無事入港。念願の九州初上陸です。うきうき♪
天気は晴天。絶好の史跡巡り日和!
早速、走るぞ!とカーナビを設定しようとするも、
驚いたことに、車はまだ神戸六甲にいるつもりでいました。。。
エンジンを切っている間はGPSが働いていないんですね(迂闊。
 何度か電源を入れなおして、やっと現在地を把握してくれたところで
何度か電源を入れなおして、やっと現在地を把握してくれたところで
太宰府へ向けて大分ICから大分自動車道で大移動!
途中AM7:45、別府湾SAで朝食をとり、
AM9:45、太宰府天満宮に到着。
御存知、菅原道真公で有名な全国天満宮の総本宮です。
太宰府天満宮には駐車場がないので、
周辺の有料駐車場に停めさせてもらって散策開始v
鳥居の前まで続く参道脇には御土産物屋さんが沢山並び、
銘菓「梅ケ枝餅」の焼ける香りが食欲をそそりました。
ちょっと列が出来ているお店のものが美味し目という
きららとんぼさんより事前情報を頂きましたので、
早速、我らも「梅ケ枝餅」を購入♪
この日は「茶房きくち」さんに列が出来てましたよv
あまり日持ちがしないということだったので、
道々食べようと思い、紙袋に入れてもらったのですが、
焼き上がりのアツアツを下さいましたvありがとうございますv
 鳥居を潜って右手には、ありましたよ!有名なあれ!
鳥居を潜って右手には、ありましたよ!有名なあれ!
「東風ふかば にほひおこせよ 梅の花」の句碑v
太宰府へ左遷された菅公を慕って、一夜のうちに空を翔けて来たという
その飛梅は本殿右側の御神木だそうです。ロマンチですねv
さて、その句碑の斜向かい。
「延寿王院」という建物があるのですが、
ここが八・十八の政変での七卿落ちの内、
五人の公卿が滞在した場所なんですよね。
公卿の一人、東久世がその日の日記に
「坂本龍馬と面会、偉人なり、奇説家なり」と感想を残していますが、
慶応元年五月に龍馬さんはここを訪れて、
薩長連合の必要性について議論を交わしたのだとか。
残念ながら外から覗き見程度しかできませんでしたが、
荘厳な御屋敷っぷりには公卿の匂いがしました。←どんな偏見だ?
 知恵がつくという信仰の通りに神牛の頭を撫で、
知恵がつくという信仰の通りに神牛の頭を撫で、
朱色の太鼓橋を渡って、楼門を潜り本殿へ。
丁度祝詞があげられている時でした。
粛々と御参りをして母上の為にお守りも買って、
「鷽(うそ)」の御神籤も引いてきましたよv
拙者は「中吉」。「旅行:親しき友と旅行せば吉」とあったので
旅のお守りに持ち帰ることにしましたv←御利益ありましたよ!
しかしながら照り付ける陽光とあまりの暑さに少々ばてた二人。
太宰府天満宮を後にして、続けて大宰府政庁跡へ。AM10:30。
 奈良・平安時代に「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた
奈良・平安時代に「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれた
中国・朝鮮半島への外交窓口であり国防の前線地だった場所です。
ちょっとした公園になっているので公園用の駐車場に停めて散策。
広々とした野原の中ほどに三つの石碑があります。
どれも明治・大正時代に立てられたもののようですが、
内「太宰府址碑」の篆額は有栖川宮熾仁親王のものだそうです。
平城京跡のちっちゃい版のような感じで、
誰も人がいなかったので開放感があってよかったです!
 噴出す汗を拭いながら、次に向いましたのは佐賀市内。
噴出す汗を拭いながら、次に向いましたのは佐賀市内。
大宰府から長崎自動車道で移動し佐賀大和ICで降り、神野公園へ。
AM12:40。ここも公園用の駐車場があります。
江藤新平さんの像を見に行ったのですが、ちょっと猫背な江藤さんでした。
この公園、もとは旧藩主鍋島直正公の別邸だったということで、
公園の中ほどには復元した「隔林亭」があり、
今は桜やつつじの名所でもあるそうですね。
この夏場は池におたまじゃくしが沢山いましたよ♪うようよよ♪
続けて、江藤新平さんのお墓参りに本行寺へ。PM1:00。
こちらはお寺にそのまま車で入るのは気が引けたので、
向かいのコンビニの駐車場に停めさせてもらいました。
 石燈籠が並ぶ参道をずんずん進んでいくと
石燈籠が並ぶ参道をずんずん進んでいくと
大きな本殿に目が奪われてうっかり見過ごしてしまったのですが、
寺務所で江藤新平さんのお墓を伺うと、
本殿の手前左側に柵囲いされた墓地を案内して下さいました。
「裁判長!私はっ…」by.『獅子〜』臨時法廷での最後の一言。
自分の作った司法制度に縋る筈が、
足元すくわれた様な形だったのが印象的でしたね。
フィクションは劇的に描かれてあるのでしょうが、
 実際…お墓参りしたら無念さが伝わってきましたよ><。
実際…お墓参りしたら無念さが伝わってきましたよ><。
御冥福をお祈り致します。
因みに江藤新平さんのお墓参りをすると
ひとつだけ願い事が叶うのだとか!
…拙者、このお盆の日にお参りできたことだけで胸一杯で
その場でお願い事して来れなかったのですが、
あとから「家内安全、無病息災」祈っときました><。
で、そんな佐賀の役つながりで、次に佐賀城址へ。
PM1:25。別名「栄城」「亀甲城」「沈み城」とも言うんですね。
 二の丸・三の丸・百間蔵などは佐賀の役で焼失した為に、
二の丸・三の丸・百間蔵などは佐賀の役で焼失した為に、
現在は佐賀の役の時の弾痕が残る「鯱の門」と
「続櫓」だけが残っているのですが、
平成16年に本丸が復元されたのですね!
歴史館として開館していたので、上がり込んで拝見してきました。
当時の柱跡を崩さないように、そのまま保存した状態で土台を築き、
その上に新たに柱を設けて建物を復元したということです。
床下の覗き窓がありました。凝ってますね。
 展示物はありがたいことに、ちょうど興味のある
展示物はありがたいことに、ちょうど興味のある
幕末・維新期の佐賀が大きく紹介されてありましたが、
…佐賀って、実は凄い藩だったんですね!開眼。
いや、どうも佐賀って「パッ」としないイメージだったので。←失礼。
が!今回、十代藩主鍋島直正を知って認識を改めた次第。
維新には目立った動きをしていなかったとはいえ!
他藩よりリードして”薩長土肥”と並び称されたのは
直正公の藩政のおかげ…稀代の名君あってこそだったのですね!
 直正をして「蘭癖大名」と称されるほど
直正をして「蘭癖大名」と称されるほど
外国の学問に取り組んでいたというのだから凄いですね。
そのおかげで藩士は海外留学も出来たんですし。
そういった学問の土台があったからこそ、
明治の政界に沢山逸材が送り込まれたということで納得。
…でもやっぱり、明治政府樹立からひょっこり現れた感があるので
漁夫の利?…とか思ってみたり。←まだまだ勉強中ですので。
因みに、偏りながらも佐賀の役を勉強してきた次第ですが、
佐賀はこの時が一番輝いてましたよね!
この時ばかりは佐賀が日本の中心だったような気さえします。
そんな渦中に彼がいたなんて。彼。そう、山川浩さん。
もうここからは山川視点で佐賀城を見学してました。
「また兵糧が少なかったんだよね…
嗚呼、あっちら辺で左腕負傷><。」
←三太さんから頂いた資料片手にこんな具合です(笑
 さてさて。視点を切り換えて、続けて大隈重信旧宅・記念館へ。
さてさて。視点を切り換えて、続けて大隈重信旧宅・記念館へ。
PM2:30。記念館は時間が惜しかったのでスルーしましたが、
敷地内に立派な像が見えたので、写真撮影させてもらいましたv
大隈重信といえば早稲田大学創立者という程度しか
認識不足で申し訳ないのですが、、、
しおりに面白い記事を見つけたので御紹介。
「怒らない人」大隈重信のストレス解消法!
癪にさわることがあると、まずお風呂に入ったそうです。
糠袋で体をごしごし擦って癇癪を和らげたとか。
それでも治まらなければ酒を一杯飲み、
なお治まらなければ寝る。そうして怒らないでいられたのだそうな。
…最後の手段は不貞寝っぽいですね(笑
 そんな珍知識を得て、次に万部島へ。
そんな珍知識を得て、次に万部島へ。
車一台がやっと通れる位の細く入り組んだ路地を
曲がって曲がって、やっとの思いでたどり着きました。PM2:50。
どうやらこの複雑な道も当時の遺構のようで、
城攻めをし難いように造られたもののようですね。
ここは代々藩主が国家安全を祈願して
万部塔を建立した場所ということで、
南手に佐賀の役の招魂碑が二つ並んであります。
 向って左にある碑には「明治七年戦死者」として、
向って左にある碑には「明治七年戦死者」として、
佐賀の役で亡くなられた方々の名前が彫られてあり、
最初に江藤新平さんの名前が確認できました。
そして右にあるのが、この見上げるほど大きな亀(獏?)の上に
聳え立つ注連縄飾りがついた立派な碑。
残念ながら逆光でよく見えなかったのですが、
妖気立つ雰囲気に圧倒されました。
聞けば、元は城内西の門と河原小路の二ヶ所に分かれていた碑を
あとで万部島にまとめたそうで、
江藤新平らが刑死した毎年四月十三日に慰霊祭典が行われるそうです。
 続きましてPM3:10。松原神社へ。
続きましてPM3:10。松原神社へ。
残念ながら神社近くに駐車場がみあたらず、
近くの有料駐車場に一時駐車。
松原神社は藩祖鍋島直茂とその先祖を合祀しており、
直茂公の法名に因んで日峰大明神ともいうそうです。
右手脇の川には河童(!)が沢山いて、なにやらおっかない感じ。
しかも境内で鶏を飼育しているらしく、悠々闊歩していました。
他に参拝者もなく、のどかな雰囲気でしたよ。
その境内を裏手に回ると、
隣り合わせで佐嘉神社の本殿があります。

 鳥居前に向うとそこありましたよ!
鳥居前に向うとそこありましたよ!
これぞ佐嘉神社のシンボル!?
神社なのに150ポンドカノン砲!それにアームストロング砲!
何故に兵器が神社にあるのかといえば、
こちらには佐賀藩十代藩主鍋島直正公と、
十一代藩主直大公が合祀されているので、
彼らに関連している物として展示されてあるのでしょうね。
 長崎防衛強化の為に直正公が日本初の洋式反射炉を設け、
長崎防衛強化の為に直正公が日本初の洋式反射炉を設け、
近代大砲を鋳造に成功するや、
ペリー来航後は日本の沿岸警備の為にもと、
幕府は佐賀藩にこの大砲を200門も注文したそうです。
今回足を運ぶことは出来ませんでしたが、
長瀬町にその築地反射炉跡があります。
また、その右手には「佐賀の七賢人の碑」がありました。
一番上に鍋島直正、中段左より、大隈重信、江藤新平、副島種臣、
下段左より、佐野常民、島義勇、大木喬任。
「近代日本の礎は佐賀出身の衛人達がつくった!」と、
佐賀の観光案内などには必ず取り上げられている佐賀の七賢人。
 この日も佐賀城址の本丸歴史館で学んできたばかりなのですが、
この日も佐賀城址の本丸歴史館で学んできたばかりなのですが、
…ふ。下段二人は覚え切れなかったよ、とほほ〜><。
と、内心嘆いていたら簡単な人物説明がすぐ側にあったので助かりました。
拙者の為の簡単解説1:佐野常民(さのつねたみ)
西南戦争で博愛社を設立し負傷者の救護にあたり、日本赤十字社の父。
拙者の為の簡単解説2:島義勇(しまよしたけ)
佐賀の役が起こると憂国党を率いて政府軍と戦った。
 さて、そんな彼らが学んだ藩校が神社近くにありました。
さて、そんな彼らが学んだ藩校が神社近くにありました。
PM3:30、藩校弘道館跡。
今は記念碑が立つのみですが、弘道館教育の触りを聞いて驚きました。
全寮制をとって全藩士の子弟を25歳まで徹底的に教育したとかで、
課業に合格しなかったら罰金ものだったそうな。…スパルタです!
佐賀藩といえば「葉隠武士道」が有名ですよね。
「武士道とは死ぬことと見つけたり」の猛烈教訓なアレです。
が、この武士道書にあるような日本古来の閉鎖性・独善性は
直正公指導のもと見直されたのだそうです。
軍事力強化の必要性から広く学問を取り入れようと教育改革が行われ、
他藩への遊学や海外留学が積極的に勧められたということです。
これを後押しする為に、直正公は藩校費用を
10倍に増加したというのですから意気込みが分かりますね。
 さあ、次で佐賀のラストになります龍造寺八幡宮・楠神社へ。
さあ、次で佐賀のラストになります龍造寺八幡宮・楠神社へ。
PM3:50。佐賀城を南に据えて、佐賀市内を東西に走る長崎街道が
最も北寄りなる場所に位置しています。
この、街道が佐賀城を離れるように走っているのも城の守りの為なのでしょうか。
とにかく佐賀市内は城に向って真っ直ぐ移動できませんよ。
龍造寺八幡宮は鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮の分霊を祀る古社ということですが、
その本殿の左隅に楠神社があります。
南朝の忠臣、楠木正成・正行父子を祀るもので、
傍らには楠木氏の家紋、菊水をかたどった碑もあります。
 佐賀で何故に楠正成・正行父子??と思いましたら、
佐賀で何故に楠正成・正行父子??と思いましたら、
寛文二年(1662年)に、佐賀藩士であった深江信渓が、
楠木正成・正行父子の忠孝を広く世に顕彰しようと発起し、
当時、佐賀藩二代藩主鍋島光茂公をはじめ、藩内の協賛を得て、
楠公父子が桜井の駅で最後の別れをしている鎧姿を
京都の仏師に頼んでつくらせたということで、
これが、楠公親子を祭った最初ものになるのだそうです。
「青葉繁れる桜井の、里のわたりの夕まぐれ…」
損傷しても修理されて、この木造は今も本殿に安置されてありました。
そして幕末、勤皇論が盛んになると、南朝の忠臣、楠木正成の人気が高まります。
佐賀藩でも思想家・枝吉神陽が義祭同盟を組織して楠公祭を実施しました。
これが佐賀の尊王倒幕運動の幕開けであり、
副島種臣、大木喬任、江藤新平、島義勇、大隈重信など
錚々たる秀才達が名を連ねたのでした。
その「義祭同盟之碑」が本殿手前に据えられてあります。
因みに薩摩藩では、有馬新七が楠公神社を設けて
大久保一蔵らが祭事に参列したといわれているそうですよ。
 というわけで、幕末佐賀巡りはこれにて終了!
というわけで、幕末佐賀巡りはこれにて終了!
猛暑の中動き回ったので初日からしてフラフラの二人。
この日は2日目に長崎入りを考えて武雄に宿をとったので、
このまま佐賀大和ICから長崎自動車道を武雄北方ICへ抜けて
PM5:30、今日の御宿、御船山観光ホテルに到着。
西日本随一の名園『御船山楽園』の中に建つ静寂の宿ということで、
幕末、鍋島藩のお殿様も時々入浴していたという名湯を
檜風呂と御影石の露天風呂でじっくり堪能させて頂きましたv