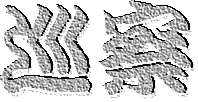
■北野天満宮の観梅 : 北野天満宮→ 上七軒→ 浄福寺→ 一条戻り橋→ 清明神社→ 下鴨神社→ 上鴨神社→ 御苑
去年の暮れあたりから家族サービスを兼ね、今回も母上と一緒に京都巡りです!
今回のテーマは観梅!!母上が今年は京都で観梅を楽しみたい!と所望しましたので
梅のメッカ!北野天満宮に行ってまいりました(^―^)
この日は連日の陽気と裏腹に酷く冷え込む気候で、天気予報では京都は
雪とのこと。観梅なだけに寒梅となってしまいました(一本!
AM11:00。阪急大宮駅にて下車。そこから毎度お馴染みの京都市バス
一日周遊券を購入して、いざ北野天満宮〜。とは行かず、まずは前川邸へ〜v
今流行の新撰組フィギュアを求めて!(笑 が、ここで酷い吹雪に!!(T■T)
雨宿りとばかりに駆け込んだ前川邸の門先で、ありました!フィギュア!
前回、霊山・前川邸で売り切れの為に購入ならなかったリベンジとばかりに
母上も乗り気で(笑)箱入り(6体)を二箱買い込み、あいかわらずの

 大雪に眉をひそめながら、懐も寒くなりましたが
大雪に眉をひそめながら、懐も寒くなりましたが
胸一杯で壬生を後にし、幸福堂できんつばも買占め、
改めて市バスを乗り継ぎ、いざ北野天満宮〜。
北野天満宮は御存知、「学問の神様」菅原道真公をお祀りした神社。
国を鎮め守る神として平安時代中期、北野の右近馬場に
菅原道真公の御霊をお祀りしたのが始まりとされています。
で、菅原道真といえば、こちらの詩ですよねv
「東風吹かば 匂い遺せよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」
東風が吹いたら、匂いを配所の私のもとまで寄越してくれ、梅の花よ。
主人がいないからといって、春であることを忘れるなよ。
昌泰四年(901)、大宰権帥に左遷され、家を発つ時の歌として
伝承されている有名な詩。切ないですね(T_T)そんな道真の
北野天満宮は、この日梅の花が満開でした!!
見て下さい!すごく綺麗な梅林v 梅といえばかの殿方達も好きですよねvvv
「梅の花 一輪咲いても 梅は梅」…道真公の詩と並べてはいけません。
 国宝の社殿は八棟造と称されるもので、総面積約五百坪の雄大な
国宝の社殿は八棟造と称されるもので、総面積約五百坪の雄大な
桧皮葺屋根の威容は、造営当時そのままに絢爛豪華な桃山文化の象徴。
威風堂々たる創りに感嘆しながらお参りをしようと正面を望めば、
長蛇の列!受験期でもあったので参拝客の多いことっ(0_0)
丁度、母上の国試も近かったので我等も列に並び、合格祈願をしてきました。
この頃になると雪雲に晴れ間が覗き、酷い吹雪がおさまったので助かりました。
PM1:30。天満宮正面の「この花」で昼食の雑炊と甘酒を頂き、
PM1:50。改めて繰り出したるは上七軒。
京都の五つの花街の一つであり、お茶屋が軒を連ねる静かなたたずまい。
歳さんも通った花街の一つであります。確か君菊さんとの間に一女…でしたっけ。
上七軒は室町時代初期に北野天満宮が焼失した際、その再建に充てた残り木で
七軒の茶屋を建てたのがはじまりとの事。なるほど名前の由来を知って納得。
遊女街として公許された古い花街です。
で、せっかくの花街なので芸妓さんの一人でもお目にかかれればいいな〜と
思いつつ、見つけた和菓子屋さんで京の芸術を楽しんでいると、着物姿の
女の方が一人入ってこられて、お菓子を八つほど注文されました。
御化粧こそしていませんでしたが物腰がどこかしっとりしてて「この方はもしや!」
と思いつつも遠目に窺っていると、「失礼ですが、芸者の方ですか?」と
大胆にも母上がいきなりコンタクト!!「はっ、母上〜っ(゚■゚;)」

 ご存じのとおり、芸妓とは、京阪の呼び方で、芸者さんのこと。
ご存じのとおり、芸妓とは、京阪の呼び方で、芸者さんのこと。
接客業の一種ですが、あくまでも芸を見せるのが芸妓さん。
その特殊な接客業の方のことを母上にちゃんと伝えていなかったので
大失敗。
「写真を一緒に撮らせて頂けませんか?」との母上のお願いに
彼女はそっけなく「お仕事中ですので」と断られたので、
母上は大ショックだったようで不快な思いをさせてしまいました。
そうなのです、京の芸妓さんは御高いのです。
私も詳しく走りませんが、その筋の友人から話を聞くところによれば
彼女たちは、日々きびしいお稽古をかさね、
花街のきちんと決まったしきたりの中で生活しており、
自分の芸で客からお金を取る職業なので、ストレートに表現してしまえば
金を出す客にはサービスするが、無銭でサービスはしないというのが芸妓だとか。
なので、観光客に写真撮影をタダでなんてさせてもらえないものなのです。
それを母上に最初に伝えれていなかったものだから、
もう母上ったらそっけなくされたことに御立腹。はうあ〜(TヮT)
芸妓さんと遊ぶならちゃんとした御座敷じゃないといけないのですよ。
そんなわけでなんとか諭して機嫌を直してもらいつつ、
気分を切り換えて次に向かうは浄福寺!
直進できなかったので上七軒より徒歩20分程、PM2:15。
 鳥羽伏見の戦の折、巨大な兵力を京都に常駐させた薩摩藩でしたが、
鳥羽伏見の戦の折、巨大な兵力を京都に常駐させた薩摩藩でしたが、
相国寺では収まり切れず、西に位置する浄福寺に分駐することになりました。
当時の地図を見るとわかりますが、今の25倍以上の広さがあったようです。
浄福寺に駐屯した薩摩藩兵は乱暴な振る舞いが多く、
いつしか「浄福寺党」と呼ばれるようになったそうです。
その荒くれ者達が残した刀傷が庫裏に今もあるとのことでしたので、
それを探しに行ってきました。…が、どれだかわかんない(゚ヮ゚;)
 これかな?あれかも?と庫裏の周りをぐるぐるしているとどれもかれもがそれっぽく
これかな?あれかも?と庫裏の周りをぐるぐるしているとどれもかれもがそれっぽく
見えてきて…「こんなに沢山傷付けて…薩摩っぽは気性が荒いなぁ」
などと感想をもらしつつ(コラ)、一番刀を打ち付けやすそうな位置にあった
「コレが、それっぽいぞ」ってのがあったので撮影してきました→
ほんと、銃弾の跡のような虫食いのような穴とかも沢山あって朽ちかけている
建物だったので確証はありません。知ってる方教えて下さい(TヮT)うえー。
さて、そのまま一条通を東に足を進め、次に向かったのは清明関係の史跡(?)
一条戻り橋、と清明神社!時代が違うよっ(^^)
浄福寺より徒歩10分程、PM2:35。
清明関係は友達が凄く詳しいのであまり下手なことは綴れないのですが、
阿部晴明は陰陽師で有名ですが、彼は実のところ天文博士。
朱雀帝(すじゃくてい)より六代の帝に天文陰陽博士として仕えました。
唐へ留学した後、わが国独特の陰陽道を確立しました。
年中行事、暦術、占法等は、この時より創られました。
 「陰陽道、奇門遁甲(きもんとんこう)に通じ式神をあやつる」
「陰陽道、奇門遁甲(きもんとんこう)に通じ式神をあやつる」
清明は祈襦呪符の一つに、天地五行を象どり万物の除災清浄をあらわす
五芒星を用いました。清明神社の社紋で俗に清明桔梗と呼ばれています。
陰陽五行思想の象徴です。呪術的な要素があるために神秘的ですね。
そも陰陽五行とは……(゚―゚;)なんて解説し始めるとどんどんドツボに
嵌っていくので、ここらへんで切り上げますが(詳しくは各自で調べましょうっ)
そんな安部晴明がまつられている「清明神社」は、堀川通りに面しています。
一条通を堀川通りに抜けると、丁度一条戻り橋に出会います。
 源氏物語には「ゆくはかへるの橋」と書かれている一条戻り橋。
源氏物語には「ゆくはかへるの橋」と書かれている一条戻り橋。
そばに清明が式神を封じ込めたといわれる穴があるのだとか。。。
今は空掘りで、ちょうど橋の上から下を覗き込んでいると、堀の下に降りて
写真撮影している方がいて驚きました(゚ヮ゚;)式神かと思いましたよっ(驚。
現在でも、”戻る”は嫌われており、葬列や入嫁列は渡らぬ習わしだとか。
橋から100mほど北上すれば清明神社があります。ちょうど訪ねた時は
鳥居の裏手が工事中で雰囲気ぶち壊し状態で残念でした(T皿T)
ついでに神社のすぐ北の西陣織会館も覗いてみてきました。
外国人向けの御土産物が多く、観光客も外国の方たちが多かったです。
で、さらに北に歩を進め、今出川通を西に進み、京都市考古資料館を訪ねました。
平安貴族愛用の陶器だとか、伏見城跡の台所から見つかった鯛の骨…
なんかを見てきました。時代に幅があるので、拙者では勉強不足で見るだけでした(泣。
資料館を後にさらに西に歩を進め、観世稲荷社を探すも…見つからず、、、
母と一緒に周辺をぐるぐる散策するも見つからず、、、どこにあるの??
観世稲荷社の井戸の水面にはいつも波紋がえがかれており、今
観世流で用いる扇の模様にも用いられているというので観に行きたかったのですが、
PM3:20。稲荷社を探していると首途(かどで)八幡宮に辿り着きました。。。
牛若丸を奥州へ誘った金売吉次の屋敷跡でその鎮守とのこと。
牛若丸がここから旅立ったというので「かどで」というのだそうです。
 さて、稲荷社は諦め、次に向かうは下鴨神社。バスで下鴨神社前まで移動。
さて、稲荷社は諦め、次に向かうは下鴨神社。バスで下鴨神社前まで移動。
PM4:15。空に陰りが見え始め、少々早足になる親子二人。
思ったとおり、再びちらほら雪が舞い始める始末。。。寒っ(0m0;
初めて下鴨神社を訪ねたのですが、南にのびる糺ノ森の鬱蒼としたこと。。。
かつては「糺すの納涼(ただすのすずみ)」と言われて王朝時代の
リクリエーションの場だったという話ですが、暗がりでしたのでまわれ〜右。
神社参拝のみにしてきました。下鴨神社といえば、久しく御所の外に
出たことがなかった孝明天皇が、文久三年三月十日、
宮部鼎蔵らの運動が奏功して行幸することとなったところです。
この行幸は上下加茂社、石清水八幡宮に参拝されましたが、
関白に加えて上洛中の将軍家茂や後見職、一橋慶喜も従いました。
 というわけで、これはついでに行ってみようかと次に足を向けたのは
というわけで、これはついでに行ってみようかと次に足を向けたのは
上鴨神社!バスで移動すること30分。PM5:00。
勢いを増す雪に阻まれつつ、下鴨神社同様に鮮やかな朱の鳥居を潜って
参拝してきました。厄を祓いあらゆる災難を除き給う厄除(やくよけ)明神、
落雷除、電気産業の守護神として広く信仰されているそうですね。
平安遷都以来、皇城鎮護の神、鬼門の守り神、総地主の神として崇められて、
今日も建築関係等の方除祈願が多くあるとか。
二つ目の鳥居を潜れば、正面にあるのが白砂で作られた円錐形の「立砂」。
神山を模った「清めの御砂」ということで、上鴨神社の象徴ですね。
鬼門などにまく清めのお砂の起源はここにあるようですよ(゚ヮ゚)
上鴨神社を後に参道を戻り際、目に付いたのが二本の大きな枝垂桜。
ほんのり色付いたつぼみが雪と寒さに哀れでしたが、立派な枝ぶりに
「桜が満開の時期になったらまた来ようね!」と母上と約束をしてきました。
 さて、あともう一踏ん張り。と日も暮れかかってなお移動する親子二人。
さて、あともう一踏ん張り。と日も暮れかかってなお移動する親子二人。
最後に向かうは京都御苑は蛤御門!
PM5:00。上鴨神社からバスで移動すること30分、府立医大病院前下車。
対面に当たる清和院御門より入ってまっすぐ砂利道を西へ、じゃりじゃり。
拙者などは何度も訪ねたことがある蛤御門。禁門の変の折の激戦地です。
これを母上には見せておきたいと思い連れて行ったのですが、やはり門に残る
弾痕に、母上も目を瞠っていました。また、長州の猛将来島又兵衛の
討死場所といわれる清水谷家のムクの木の処で写真を一枚。。。
撮ったところ…「何か写ってる!?」(゚ん゚;)も、もしや、、、来島さんですか!?
なんて、、、ただの白くなった息が映りこんでしまったもよう。。。だよねっ!?
↑拙者、物の怪やら幽霊やらおどろおどろしたものは苦手でござるっ(TヮT)
 そんなわけで、最後に肌に感じる寒さが二割増になりましたが、、、
そんなわけで、最後に肌に感じる寒さが二割増になりましたが、、、
今回も無事旅程を終えて帰宅。そして早速紐解くお土産の数々!
父上も一緒になって熱中したのが買い込んできた新撰組フィギュア!
精巧なつくりに「凄いな〜凄いな〜」とはしゃぎつつ、出来上がったフィギュア。
が、どうも不自然で「なんか不恰好だなぁ…」と思っていたら
腕や足の向きを反対につけてしまっていたりして、家族でわたわたしながら
全部のフィギュアを組み立てるのに2時間ほど費やし…←アホ。
「まんまと嵌ってしまったな…」と御満悦。後日、さらに20体程買い込み←アホや。
土方さんの黒羽織バージョン以外は揃えましたよっ!!←アホや〜。。。
→で、一体どこに保管しているのか謎な写真ですね〜。実は寿司桶の中っす(笑。