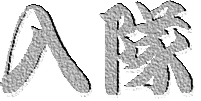
■ 新撰組隊士 人物・経歴 紹介
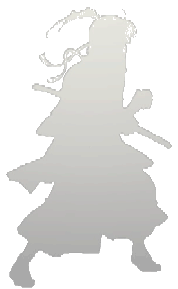 新撰組隊士達の経歴をさわり程度に御紹介。
新撰組隊士達の経歴をさわり程度に御紹介。調べてみて、結構不明な個所か多いことに驚きます。
たかだか130年程度前のことだけど…(人間で言えば4・5世代前ってことになるかしら?)
江戸時代、戸籍を管理するとかいったシステムがなかったのか?
正月にいっせいに歳をとる時代、誕生日すら覚えるなんてことしない時代だし。
う〜ん…今じゃ、他人様の戸籍を調べることできませんしねぇ…(-_-)>
散々調べ尽くされたと思っていても、
見落としやまだ眠り続けている史料はあるはず。
研究書なんかに載っていることって、結構関係ないところから
ぽろっと出てきた物なんですよっていう話もありますし。
新撰組だってまだまだ知られていないことがあると思うとワクワクしてきますねv
あの時誰がどうしていたのか! この時誰は何をしていたのか!
知りたいこと、謎に思うこと、当人達にしてみれば「ほっとけよ!」と思えることまで(笑。
が、…ふと、「覗き根性に似ているかもしれない…」と思いました(/TmT)/
他人様の人生勝手に覗き見してるような、そんな感覚…?
…う〜ん・・・いくら時の人だからといっても、これって犯罪チックかも!?
歴史研究家の方って、どういった姿勢で調べているんでしょうかね?
ま、是非はともかく拙者が新撰組入隊の際(FANになってから)、
ちょいちょい調べた主要人物の履歴を御紹介。
(不確かなものが多く、詳細は大幅にCUTしちゃってますので御了承を。)
|
BACK |



 ← 幅広い知識と教養を身につけた文武両道の人で、壬生の人からも信頼される方だったようです。彼の新撰組隊士としての活躍を記録したものは少ないながら、強烈な切腹エピソードを残しました…。新撰組史七不思議の一つです…謎。
← 幅広い知識と教養を身につけた文武両道の人で、壬生の人からも信頼される方だったようです。彼の新撰組隊士としての活躍を記録したものは少ないながら、強烈な切腹エピソードを残しました…。新撰組史七不思議の一つです…謎。



 ← 撃剣師範でもあったように、剣の腕は沖田・永倉・斎藤と並ぶほどであったとも言われています。また若い隊士達の世話もして面倒見の良い人だったようです。南部藩邸で切腹に際し、遺品を故郷の家族に届けるよう血文字でしたためたという泣かせるあのエピソード…実は虚構らしいです(T_T)
← 撃剣師範でもあったように、剣の腕は沖田・永倉・斎藤と並ぶほどであったとも言われています。また若い隊士達の世話もして面倒見の良い人だったようです。南部藩邸で切腹に際し、遺品を故郷の家族に届けるよう血文字でしたためたという泣かせるあのエピソード…実は虚構らしいです(T_T)

