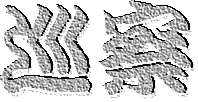
| 平成十六年 二月十一日 |
前日に京阪沿線駅構内で配布していた霊山歴史館「大新撰組展」のチラシをGET。 即、京都行きを決定して今回もまた京都洛中を練り歩いてきました(笑)
今回の巡察は母上と一緒。拙者がなんのかんのと新撰組を無差別布教しているので
京都駅に降り立って、すぐに見つけて駆け込んだのが大河「新撰組!」のパネル展。
塩小路通を西へ徒歩10分弱。リーガロイヤルホテル京都前(陸橋手前)に
屯所の広さは一万㎡。伏見奉行所へ引き払うまでの半年間、
碑の横に説明書きがあるのですが、「移転に際し、土方歳三の指示で
屯所跡を後にそのまま北上して西本願寺手前の興正寺へ。
太鼓楼を後に、花屋町通を西に抜けて向ったのは島原。
以前、『そら色のだんだら』のそら太さんに連れて来てもらってから
で、食前酒に濁り酒が出されたのですが、これが美味!
「無理なこと聞いちゃ駄目じゃないさ…」と母上を嗜めていると、
さて、御腹も頃合になったところで今日の主目的、霊山歴史館
2004/1/3~2004/3/21はⅠ期「新撰組 誕生」ということで、
で、入って正面に据えられた木砲にビビリつつ…(客を狙うとは不逞ぇ奴だ。)
二階に上がれば階段すぐのところに慶喜と竜馬さんの等身大パネル。
とにかく人が多くて、展示物を見るのも押すな押すなの混雑ぶり。
さすがというべきか大河影響って凄いですね。すでに心無い観光客が
…といった注意を呼び掛けるよう、行くところ行くところで協力を願われるくらい
で、そこにもフルタのフィギュアを発見。…やっぱり売り切れでした(泣。
前川邸の次には八木邸へ。こちらでは毎度おなじみの屯所餅を購入して
今日は二人とも数珠を持ち合わせていなかったのでお墓参りは
また高台に位置するので境内から京の街のイルミネーションが綺麗に見えました。
|
| 平成十六年 二月十四日、二十一日 |
ことの起こりは一本の電話。 「D×Iさん、京都駅の大階段駆け上がり大会に新撰組で出ませんか?」
御世話になってます京都龍馬会のひとしさんから唐突に連絡が入りました。
それから二週間ほどして、またまたひとしさんより至急の連絡が。
14日、PM2:00。近江屋跡の真裏あたりにあたる称名寺で京都龍馬会の方々と
会議が終わってから着替えに移り、拙者はまだ着慣れていないこともあり
つい先日訪ねたばかりの霊山歴史館を背に、護国神社が撮影の場ということで、
そうこうしていると、PM3:00。KBS京都テレビの方々がいらっしゃって
で、撮影ですが、、、先に謝ります。「 申 し 訳 ご ざ い ま せ ん 。」
まずは名乗るということで近藤さん(役名)や土方さん(役名)は
腕の長さにあっていないのかと刀のせいにしてみたものの、(←素人丸出しですね…御恥ずかしい。)
新撰組側と竜馬側で撮影を区切っていったのですが、竜馬側では
怪我せず終えれたので良かったですが、こんな大変な撮影になろうとは。。。
なにやら終わってみればバタバタとした2時間あまりのことだったのですが
で、撮影の後、称名寺に戻って着替えてから御開きとなり、
好き者同士で幕末談義にもりあがり(笑)一息ついたところでひとしさんは拙者を
そんなノリで、帰り際。南海堂さんが毎月出されているという「南海堂通信」という
▼
というわけで、あっというまに一週間。▼ ▼ というのも仕事がメラ忙しくって、先取りの撮影をした翌日の 日曜日からして休日出勤した挙句、一週間ぶっ続けで 帰りのバスがなくなるまで働き詰め状態。 もう大会当日は気を抜けば一寸先は霞んで見えるといったような 最悪のコンディションで大会に臨むことに…ふらり。。。
大会前日、隊長のN氏(近藤さん)より連絡が入り、
しかし!京都駅に降り立った途端、お祭ムードに覚醒!(笑)
そうこうしていると時間になり、皆さんと合流して早速着物に着替えて
そんな中、目を引いたのは東映さん。コスチュームがやはり本格的!
さてさて、本題の階段駆け上がり大会ですが、ルールは簡単。
次々と打ち出されていく高タイム。女性でも30秒を切る人もいて
天候は良好。日中は春の陽気で、最高気温は19,6℃(京都地方気象台調べ)。
完走すれば通常レースの参加者達には「認定書」なるものがあったのですが
そうそう。レースは無事終えたのですが最後にとんでもない
そんなこんなで怒涛の大階段駆け上がり大会。怪我もなく終われたので
---------------------------------------------------------
|
| 平成十六年 三月七日 |
去年の暮れあたりから家族サービスを兼ね、今回も母上と一緒に京都巡りです! 今回のテーマは観梅!!母上が今年は京都で観梅を楽しみたい!と所望しましたので 梅のメッカ!北野天満宮に行ってまいりました(^―^)
この日は連日の陽気と裏腹に酷く冷え込む気候で、天気予報では京都は
AM11:00。阪急大宮駅にて下車。そこから毎度お馴染みの京都市バス
雨宿りとばかりに駆け込んだ前川邸の門先で、ありました!フィギュア!
北野天満宮は御存知、「学問の神様」菅原道真公をお祀りした神社。
で、菅原道真といえば、こちらの詩ですよねv
東風が吹いたら、匂いを配所の私のもとまで寄越してくれ、梅の花よ。
昌泰四年(901)、大宰権帥に左遷され、家を発つ時の歌として
見て下さい!すごく綺麗な梅林v 梅といえばかの殿方達も好きですよねvvv
PM1:30。天満宮正面の「この花」で昼食の雑炊と甘酒を頂き、
京都の五つの花街の一つであり、お茶屋が軒を連ねる静かなたたずまい。
で、せっかくの花街なので芸妓さんの一人でもお目にかかれればいいな~と
「写真を一緒に撮らせて頂けませんか?」との母上のお願いに
私も詳しく走りませんが、その筋の友人から話を聞くところによれば
それを母上に最初に伝えれていなかったものだから、
浄福寺に駐屯した薩摩藩兵は乱暴な振る舞いが多く、
ほんと、銃弾の跡のような虫食いのような穴とかも沢山あって朽ちかけている
さて、そのまま一条通を東に足を進め、次に向かったのは清明関係の史跡(?)
清明は祈襦呪符の一つに、天地五行を象どり万物の除災清浄をあらわす
そも陰陽五行とは……(゚―゚;)なんて解説し始めるとどんどんドツボに
橋から100mほど北上すれば清明神社があります。ちょうど訪ねた時は
ついでに神社のすぐ北の西陣織会館も覗いてみてきました。
資料館を後にさらに西に歩を進め、観世稲荷社を探すも…見つからず、、、
二つ目の鳥居を潜れば、正面にあるのが白砂で作られた円錐形の「立砂」。
上鴨神社を後に参道を戻り際、目に付いたのが二本の大きな枝垂桜。
PM5:00。上鴨神社からバスで移動すること30分、府立医大病院前下車。
なんて、、、ただの白くなった息が映りこんでしまったもよう。。。だよねっ!?
→で、一体どこに保管しているのか謎な写真ですね~。実は寿司桶の中っす(笑。
|
| 平成十六年 四月七日 |
先の階段駆け上がり大会から御世話になってます 「京都新撰組町作りの会」よりお誘い頂きまして、 またもや新撰組で出動です(笑。今回は春の全国交通安全運動(^―^)
というわけで、この日は会社は有休をとって(すいませんっ)臨みました。
が、またしても事前に多くは知らされず、よく分からないままに当日を向かえ、、、
カウンターの方に今日のパレード参加の旨を伝えて案内して頂き、
そこで今回ご一緒する方々と改めて顔合わせをさせて頂きました。
そんなこんなで、やはり好きな者同士、すぐに意気投合して
さて、河原に降り立てば対岸からサクラの花吹雪v そして早速始まる撮影大会!(笑。
三条通りを西へ進み、三条小橋を渡って池田屋跡の前も横切り、
河原町三条交差点での摘発活動では「交通安全を心掛けてください」、
時間にしてみれば三時間ばかりだったので、このまま終わるには
で、まんまと大はしゃぎ。そしてここでもやっぱり撮影大会です(笑
そして今日は、とある方からの紹介で前川邸へ御邪魔させて頂きました。
前川邸の蔵、といえば。御存知、古高俊太郎の拷問蔵です。が、
修復されて内部は綺麗に仕上げられたものでしたが、
では、いよいよ二階へ参ります。
今回は残念ながら、丁度新撰組展が催されていて所蔵の
さて、感動も一入のところ本日最後の〆とばかりに
|
| NEXT ⇒ |