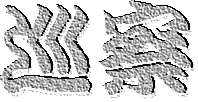
■加賀百万石散策、井波~高岡 : 瑞泉寺→ 井波八幡宮→ 井波城→ 高岡大仏→ 高岡古城公園→ 利長墓所
私用で富山に行きました際に一日フリーとなったので
井波と高岡を散策してきました。今回は事前の下調べ無しで
行き当りばったりの一人巡察だっただけにドキドキでした(^―^)←冒険好きv
 →は毎回北陸の旅行の際に立ち寄る北陸自動車道SAの尼御前。
→は毎回北陸の旅行の際に立ち寄る北陸自動車道SAの尼御前。
源平合戦の余韻さめやらぬ鎌倉時代初期のこと。
実兄である源頼朝に追われた源義経が弁慶らを従え、
この地方に落ちのびた際、義経一行に付き従っていた
一人の尼が、一行の足手まといになることをおそれ、
義経らの無事を祈りつつ断崖絶壁から荒れる日本海に
身を投げ入れたという言い伝えがあります。
天気も良かったので海を撮影しようとSAの裏の
公園を歩いていましたら、この尼御前の像の前で
祭か何かの練習かで話太鼓の演奏をやっていたので
日本海の波の音と一緒に鑑賞してきました♪
さて散策レポートですが、スターと地点は井波の旧駅前。
井波駅の駅舎は、鉄道廃止の後も町の玄関口として
バスターミナルや町の観光物産館として使われています。
 一見、お寺みたいな重厚な建物なので「これがバス亭?」と
一見、お寺みたいな重厚な建物なので「これがバス亭?」と
最初恐る恐る中を伺いました。ら、年季の入った木の椅子が
歴史を感じさせるものでした。が、…時刻表を見て唖然。
一時間に一本。時間によってはバスが無い状態…
移動手段はバスだけなので気を付けましょう。
この寺院建築の駅舎は昭和九年(1934)瑞泉寺の建立を勅願された
後小松天皇の五百回聖忌法会にあわせて建設されたもの。
この地出身の寺社大工で、東京の築地本願寺の建築も手がけた
松井角平さん(松井組)が施工。
松井家は加賀藩のおかかえ大工として代々
瑞泉寺の再建、補修に携わってきたということです。
平成八年に登録有形文化財の指定を受けています。
 井波といえば古刹瑞泉寺の門前町として栄えて、
井波といえば古刹瑞泉寺の門前町として栄えて、
寺社を手がける大工や欄間彫刻が盛んなことで有名な処。
瑞泉寺再建に端を発し、欄間・獅子頭・天神様などの
伝統工芸品を生み出した井波彫刻は、昭和五十年に
国の伝統的工芸品に指定されました。
町では沢山の木彫刻店があり、町を歩いていると
通りのそこかしこから木槌の音が響いています。
木の香が香る伝統と歴史の町。拙者の叔父さんも欄間彫りで、
よく木屑で匂い袋とか作ってくれましたv
 AM9:00。まず駅舎を後に向った先は瑞泉寺。
AM9:00。まず駅舎を後に向った先は瑞泉寺。
明徳元年(1390年)、浄土真宗本願寺5代門主
綽如上人(しゃくにょしょうにん)が、建立した瑞泉寺。
ということで寺へ続く八日町通りの手前に上人の像があります。
瑞泉寺建立の由来ですが、明徳元年、綽如上人が
京都へ向かう途中、此の地に来た時乗っていた馬が前に進まず
地面を蹴ったところ、そこから清水が湧き出たと伝えられています。
綽如上人はこの不思議さに感激されて、この地に
めでたい泉の湧き出る寺、すなわち瑞泉寺を建立されたといいます。
→上人の像はその時の様子を表したもの。
またこれが転じて井波の地名の由来となったとか。
瑞泉寺の表参道である八日町通りには、
現在も古い町並みが残っていて、坂を上りきるまでに寄り道し放題(笑
途中で、観光協会(?)があったのでパンフレットを失敬して散策開始。
 正面突きあたりの階段をのぼればそびえたつ重厚な山門。
正面突きあたりの階段をのぼればそびえたつ重厚な山門。
入り口からみごとな彫刻に目を奪われます。
素人の目から見ても「ほぅ…」と溜息が出るくらいです。
御堂の受付の方から瑞泉寺の至るところに施されている
彫刻の技巧の数々を伺いましたが、神獣や龍などの
仮想の生き物を模ったものが多く、それ故か幻想的な空間でした。
手元のMAPを頼りに次に足を向けたのは井波八幡宮。
とにかく今回の巡察は行き当りばったりなので
旅の無事を祈る為に行ってみたのですが、
 これがまた幻想的っ(感動! 御宮さんっって感じ!!
これがまた幻想的っ(感動! 御宮さんっって感じ!!
明徳四年(1393)に、山城国男山八幡大神を勧請し
八幡宮と称したことがはじまりと伝えられています。
その後、正保二年に近郷四八ヵ村の惣社として、
井波城の本丸土居の上に建立されたということで、
井波城跡がここの横手にあります。←この跡散策v
天保四年に八幡神を祀る四角神輿一社による巡幸が始められ、
続いて天保十二年に神明神を祀る八角輿、
天保十四年には諏訪明神を祀る六角輿が完成。
今も五月上旬に巡幸が行われ、「よいやさ祭り」が催されるとのこと。
 その井波城ですが、井波八幡宮の左横手の脇道の先。
その井波城ですが、井波八幡宮の左横手の脇道の先。
と、その手前で石垣の中程にある小さな門をくぐってみれば
臼浪水というのを発見。←とにかく手当たり次第覗いてみる(笑
どうも、かつての井波城の本丸跡にあたるそうで、
先に説明した馬が見つけた清水の場所がここだということで、
後に臼の胴を入れたので臼浪水と称したのだとか。
臼浪水、馬蹄石と並び浪化上人の筆と伝えられる標石が建っています。
この臼浪水は、「馬見の井戸」とも呼ばれ、その脇に
瑞泉寺12代桃化上人が建てたという小さな御堂があります。

 さてさて井波城ですが、井波城は越中一向一揆の
さてさて井波城ですが、井波城は越中一向一揆の
総本山、瑞泉寺が築いた「一向一揆の城」。
城の遺構はほとんどありませんが、分厚く高い大土塁が
古城公園と八幡宮を取り囲むように残っています。
八幡宮の社殿裏には物見台らしき
櫓台まで残っているといいます。調べてみれば
この巨大土塁を築いたのは佐々成政であるとか。
天正九年、瑞泉寺7代顕秀のときに富山城主
佐々成政と戦い、堂舎・町屋ことごとく兵火に罹り落城。
佐々成政は、井波城を大改修して家臣の
前野小兵衛勝長を守将としましたが、天正十三年
豊臣秀吉の佐々征伐の時、金沢城主
前田利家に攻められ落城。井波城は前田氏の
持城となりましたが、やがて廃城となったということです。
そしてなぜかそこに佇む神武天皇(右)→ なにか由来があるのでしょうが不明。
因みに左は松島大杉(左)→ 井波城の大手門側に当時からあったといわれる
杉の老木で、瑞泉寺建立時からあったとすれば樹齢約600年!
井波の街の歴史を見守ってきた天然記念物、松島大杉です。
 AM11:00。あらかた瑞泉寺の周辺を散策したので、少し足を伸ばして
AM11:00。あらかた瑞泉寺の周辺を散策したので、少し足を伸ばして
「井波彫刻の里」へ。観光客用の井波彫刻の紹介ミュージアム兼、
御土産物屋さんなので、ここでしばし小休憩。
サイトで御世話になっている方々に御土産を買い込み。。。
荷物を重くして(失敗でした…歩く時は身軽でいたいのに)
井波駅に引き返し、バスで高岡へ大移動!!一時間ほどかかります。
PM1:00。高岡の駅前ですぐ目にするのが大伴家持像。
越中在任の天平十八年(1746)から五年間は歌人家持の絶頂期。
自然と人情に恵まれて220余首もの歌を詠んだということです。
 家持像を後に「すえひろーど」を直進して関野神社に参拝。
家持像を後に「すえひろーど」を直進して関野神社に参拝。
そのまま北上して高岡郵便局の前まで行くと御本陣跡を発見。
高峰公園を横切って迷路小路(←おもいっきり迷子になりました)
を彷徨いつつ北上して辿り着いたのは高岡鋳物発祥の地。
格子造りの街並が残るという金屋本町の通りをぶらぶら歩き、
とおりに並ぶ昔ながらの町屋通りを楽しみました。
が、ここでふと不安になったのが人とまったく会わないということ。
朝一から散策していてずっと不安だったのですが、この日
人との遭遇率がべらぼうに低いんです。ありえないくらい会わなさ過ぎて
一人旅もちょっと独りぼっち過ぎて心配になるくらいでした。。。
人口が少ない?ゴーストタウンっぽく思えてきて自然早足になりました(笑
 金屋町を過ぎて旧南部鋳造所のキュポラと煙突を見学してから
金屋町を過ぎて旧南部鋳造所のキュポラと煙突を見学してから
進路を南にもどして次に向ったのは高岡大仏。
奈良、鎌倉に次ぐ日本三大仏の一つということだったので
見学に行ったのですが、、、
奈良の大仏と比較したのがまずかったかしら(ー_ー;)
屋外にそのまま仏様が鎮座しているのですが、
思いのほか小さかったのでがっかり。。。
ちょうどこの日、大仏様の前でお祭をしていたようでした。
で、大仏様の正面左脇に見つけた「寄贈 高岡市出身漫画家
ドラえもん 藤子不二雄殿 昭和六十一年」なる立て札。
植木がちょんまりとありました。藤子不二雄先生って高岡出身だったんですね!?
 PM2:20。大仏を背に右手へ徒歩15分。高岡古城公園へ。
PM2:20。大仏を背に右手へ徒歩15分。高岡古城公園へ。
慶長十四年(1609)、前田利家の息子、加賀藩二代藩主
前田利長が開いた高岡城は、大阪夏の陣の後、
廃城となりましたが水濠や土塁は残されて、約21万㎡の敷地が
城跡公園となって地域住民の憩いの場とされています。
二の丸に設けられた市民会館と図書館を過ぎた先の
だだっぴろい芝生の公園広場では家族連れがフリスビーとかして遊んでて
拙者も芝生に腰をおろしてくつろいできました。ごろごろごろ~。
本丸に位置する本丸広場が芝生公園になっているようでした。
 その芝生公園の端に見つけたカッコいい騎馬像は利長のもの。
その芝生公園の端に見つけたカッコいい騎馬像は利長のもの。
すでにここまででも歩き疲れでふらふらしていたのですが、
悲鳴をあげる足に鞭打って中ノ島、小竹薮、三の丸まで見て周り、
鍛冶丸に設けられた博物館があったので見学ついでに
資料漁りしてきました。最近博物館ってファイルに綴れる
資料が配布されているのでありがたいですね!がっさがっさ。
資料館を後に大手口へ向えばそこには高山右近の銅像が。
高山右近といえば安土桃山から江戸初期にかけての
代表的なキリシタン大名で有名ですね。…が
 それしか歴史の授業で習ってなかったので、なんでこんな所に右近が…?
それしか歴史の授業で習ってなかったので、なんでこんな所に右近が…?
と帰ってきてから調べなおしてみれば、
摂津国(大阪府)高槻城主となり織田信長に仕え、
豊臣秀吉により明石に移封されるも、秀吉のバテレン追放令を拒否して追放。
後に加賀前田家に高禄で迎えられ、利長にも重用され、
慶長19年(1614)正月に徳川幕府の禁教令により、国外追放となるまでに
築城の名手として金沢城や高岡城の縄張りを行なった。とのこと。
因みに右近は通称で名は長房、友祥、重友。
生まれは大和国(奈良県)、沢城主・高山飛騨守図書の嫡男。
秀吉の時に利休七哲のひとりとされ南坊等伯と号する
茶人でもあり、文武両道に優れたといいます。
 PM4:00。日も暮れかけてきたので最後に利長墓所へ。
PM4:00。日も暮れかけてきたので最後に利長墓所へ。
中学校を横切って石燈篭が立ち並ぶ参道を進めば鬱蒼と茂った
林の中にひっそり佇む石塔。林の間から中学校のグラウンドが
伺えるのですが、一人できて後悔しました。とっても怖かったです(0■0;)
だって一日を振り返って人とまったく会わないしっ墓所暗いしっ!!
そんなわけで長居したくなかったのですが、この利長の石塔は
武将のものとしては全国一という高さ。11.75mあるそうです。
そこには感嘆しつつ、そそくさと石燈篭の参道を引き返せば
足元にどんぐりがいっぱい落ちていたので記念にいくつか拾って戻りました。
 夕日が落ちる前に駅まで戻りたかったので
夕日が落ちる前に駅まで戻りたかったので
八丁通をつかつか歩き高岡駅へ。
八丁通は瑞龍寺(今回参拝しませんでしたが、
利長の菩提寺曹洞宗の名刹)と利長墓所とを結ぶ白い石畳の参道で、
114基の石燈籠(現代風オブジェ)が並ぶ松並木。
まーっすぐなその参道の長さ、約八町=870m。
今回も井波の街と高岡の街を徒歩でがんがん歩き廻ったので、
駅に辿り着いた時には足が限界でした。←無茶し過ぎ。
今回も無事に旅が出来たことを感謝しつつ、巡察で収穫した
土産と資料の重さによろめきながら井波・高岡の巡察終了!