| 文久三年(1863) | |
| 2月4日 |
清河八郎・山岡鉄太郎らの呼びかけにより、将軍ご上洛お先供有志浪士隊が結成される。近藤勇・土方歳三・沖田総司ら試衛館一派もこれに参加。 |
| 2月8日 |
幕府浪士組が江戸小石川伝通院を出立して京都に向かう。 |
| 2月23日 |
幕府浪士組が京都に到着し、洛外壬生村に分宿。本部は新徳寺、近藤らは八木源之丞宅に寄宿。 同夜、清川八郎が新徳寺に浪士を集め、尊皇攘夷の意思を表明する。 |
| 3月3日 |
浪士組に東下の命が下る。 |
| 3月4日 |
■十四代将軍徳川家茂上洛。 |
| 3月10日 |
清川八郎の狐ぶりに浪士隊分裂し、近藤勇・芹沢鴨らは京都守護職の会津藩主松平容保に嘆願書を提出する。 |
| 3月12日 |
京都残留浪士24名…芹沢鴨、新見錦、近藤勇、山南敬助、土方歳三、沖田総司、井上源三郎、永倉新八、原田左之助、藤堂平助、平山五郎、平間重助、野口健司、粕谷新五郎、阿比留鋭三郎、殿内義雄、家里次郎、根岸友山、遠藤丈庵、上城順之助、鈴木長蔵、清水五一、斎藤一、佐伯又三郎 残留組他の浪士隊が江戸へ出発。壬生村に残留した近藤らはが、京都守護職・会津藩主松平肥後守容保御預かりとなり、壬生浪士組と改める。京都市中警護を開始。 |
| 3月24日 |
殿内義雄暗殺。浪士組最初の犠牲者が出た。 |
| 4月2日 |
近藤ら、大坂平野屋五兵衛方で百両を借用し、制服羽織の作成資金とする。 阿比留鋭三郎病死。 |
| 4月18日 |
■清河八郎暗殺 |
| 4月21日 |
壬生村浪士隊、将軍・家茂の下坂に従い、道中警護にあたる。 |
| 4月24日 |
家里次郎切腹。 |
| 6月3日 |
壬生浪士組、大坂・蜆橋にて大坂力士と乱闘事件を起こす。 |
| 6月13日 |
将軍家茂東下にあたり将軍警護のため大坂・天保山まで出張。 |
| 8月10日 |
佐伯又三郎斬殺される。 |
| 8月12日 |
芹沢ら、生糸商大和屋庄兵衛方を焼き打ちにする。 |
| 8月18日 |
八月十八日の政変 13日、「来る8月20日、天皇は攘夷祈願のために大和へ行幸される。続いて、攘夷親征のために伊勢神宮に参拝される」と朝廷が発表しました。これは尊皇攘夷派の長州藩による政治工作で、天皇の傍を固める公卿に手が回され、行幸・参拝に乗じて江戸へ攻め上り幕府を倒そうという策略でした。
これに対して公武合体派の薩摩藩・会津・淀の三藩はクーデターを計画!18日夜、薩摩系の公卿・中川宮によって孝明天皇の勅許を得、長州系の公卿に禁足、つまり御所への出入り禁止を命じ、長州藩の堺町御門護衛を解いたのでした。
この日初めて壬生村浪士隊は正式に会津藩より出動が命じられ、御所内お花畑に出陣して御所の南門を守りました。
一夜にして朝敵となった長州藩は、長州系の公卿・三条実美らと共に都落ちしました。 |
| 8月24日 |
土方歳三、三条畷手で古東領左衛門を逮捕。 |
| 9月xx日 |
祇園山緒にて局長新見錦切腹。 |
| 9月18日 |
近藤ら、芹沢鴨・平山五郎の両名を八木邸にて暗殺。 |
| 9月25日 |
禁門の変の功により、朝廷より下賜金を拝領。この頃に壬生村浪士隊は、武家伝奏より「新撰組」の名と京都市中警護の職を拝命する。 |
| 9月26日 |
御倉伊勢武ら長州の間者三名を斬殺。 |
| 10月10日 |
近藤、諸藩周旋方会議に出席。 |
| 10月15日 |
幕府の禄位給付を辞退。 |
| 10月21日 |
天然理心流門人の松本捨助が入隊を希望して上洛するが、長男は家督を継げと拒否される。 |
| 12月27日 |
野口健司切腹。 |
| 元治元年(1864) |
|
| 1月2〜15日 |
新撰組、将軍家茂の下坂に従い、道中警護にあたり大坂出張、上洛随従。 |
| 3月27日 |
■天狗党の乱
武田耕雲斎ら、筑波山で挙兵。 |
| 5月3日 |
近藤、幕府に対して攘夷決行の建白書を提出。新選組の進退伺いを持ちかける。 |
| 5月20日 |
大阪西町奉行傘下の与力内山彦次郎殺害される。近藤、沖田の仕業とされている。 |
| 6月5日 |
池田屋騒動 早朝、木屋町の桝屋喜右衛門を捕縛。土方が拷問にあたり、本名を古高俊太郎と判明。また、過激派浪士による御所焼き討ちの企てを吐かせました。大火の混乱に乗じて会津藩主・松平容保を暗殺し、帝を長州へ、というとんでもない企みでした。
そしてその日の夜、過激派浪士達の会合に奇襲を掛けるべく、鴨川を挟んで会合がもたれそうな東西の旅籠をしらみつぶしに捜索します。ついに古高奪還を謀議していた池田屋の会合を見つけ、近藤、沖田、藤堂、永倉、近藤周平の六名が池田屋に突入! 激闘は二時間にも及び、宮部鼎蔵(肥後)、吉田稔麿(長州)、北添佶麿(土佐)ら七名を殺害、二十三名を逮捕しました。
この騒動の報せを受けた長州藩のうち、急進派の来島又兵衛・久坂玄端らは直ちに上洛を決意! 後の蛤御門の変を引き起こすことになります。 後日8日に近藤は池田屋事件の顛末を故郷に報じています。 |
| 6月10日 |
明保野亭事件 市中警護支援として新撰組の応援に出動していた会津藩士柴司が、清水産寧坂の明保野亭で土州家老福岡宮内組士の麻田時太郎を誤って槍で突いてしまいました。麻田が翌日のうちに自刃してしまった為、事態収拾の為に12日柴も自刃。武士のなんたるかを物語る事件です… |
| 6月24日 |
長州兵の進軍が京都に迫り、攻撃に備えて武田街道銭取橋付近に新撰組布陣。 |
| 7月16日 |
佐久間象山の子、恪次郎が父の仇討ちを目的に食客として入隊。 |
| 7月18日 |
蛤御門の変 御所に発砲した長州軍を退け、新撰組は九条河原へ出陣! 6月22日、来島又兵衛の率いる長州軍は、京都を包囲しました。武力を背景にして、八月十八日の政変以前の状態に戻すよう朝廷に訴えました。
が、薩摩藩士・西郷隆盛の工作によって朝廷は長州追討を決意! 長州軍もまた、孝明天皇を長州へ動座させるべく御所突入を決意しました。
長州軍はついに御所西側の蛤御門に殺到! 迎え撃つ会津軍・薩摩軍と激突しました。薩摩軍の近代装備の前に長州軍は成す術もなく敗退…来島又兵衛・久坂玄端は戦死。
この後、朝廷・幕府は長州藩を壊滅させるべく、長州征伐へと乗り出すことになります。 |
| 7月21日 |
新撰組、真木和泉ら十七人を天王山に追い詰めて自刃させる。 |
| 8月2日 |
■第一次長州征伐
将軍家茂より、長州征討の命が下る |
| 8月4日 |
幕府より池田屋事件の恩賞を賜る。 |
| 9月9日 |
近藤、永倉、尾形俊太郎、武田観柳斎、武家伝奏警護と隊士勧誘に江戸へ東下。
藤堂が同門を頼り、伊東甲子太郎らの入隊を得る。
近藤、老中を訪ね将軍上洛と長州追討を請願。近藤、神田の医学所に松本良順を訪ねる。
|
| 10月27日 |
近藤一行、帰京。伊東甲子太郎、同士と共に上洛して新撰組に入隊する。 |
| 11月27日 |
蛤御門の戦功で幕府より恩賞を賜る。 |
| xx月xx日 |
長州征伐を想定して「行軍録」を編成。 |
| 慶応元年(1865) |
|
| 1月8日 |
石蔵屋事件 谷三十郎ら、大阪城焼き討ちの企てを阻止すべく大坂の石蔵屋を襲撃し、土佐藩士大利鼎吉を斬殺する。 |
| 2月23日 |
山南敬助、脱走の罪により切腹する。介錯は沖田総司。 |
| 3月xx日 |
土方、伊東、斎藤、藤堂ら、隊士募集のため江戸へ。品川竹次郎・神田松吉らが新撰組に入隊。 |
| 3月10日 |
壬生の屯所を引き払い、西本願寺内の北集会所に移転。八木家に礼金として五両を渡し、唖然たらしめたという。 |
| 4月27日 |
隊士募集のため江戸入りしていた土方らが、新入隊士五十三人を率いて江戸を出立。 |
| 5月xx日 |
新入隊士増加により隊の新編成が行われる。 |
| 5月12日 |
■第二次長州征伐
幕府、和歌山藩主徳川茂承を征長先鋒総督に任ずる。 |
| 5月22日 |
将軍家茂上洛にあたり、三条蹴上まで出迎えて二条城まで警護同道。近藤、木屋町の宿泊先に将軍に同行した松本良順を訪ねる。 |
| 5月25日 |
将軍下坂に伴い、伏見街道藤ノ森まで警護同道する。 |
| 8月xx日 |
第二次長州征伐を想定して、新たに総勢百九十三人に及ぶ「第二次行軍禄」を編成。 |
| 9月1日 |
松原忠司、切腹傷の悪化により死亡。 |
| 11月14日 |
近藤、伊東、武田観柳斎、山崎烝、吉村貫一郎ら八人の隊士、幕府の長州訊問使永井玄播守主水正に随行して広島へ。 |
| 12月11日 |
長州訊問使一行は帰路につくが、近藤ら新選組は残留し、岩国方面を探索。 |
| 12月22日 |
近藤ら帰京。 |
| 慶応二年(1866) |
|
| 1月21日 |
■坂本竜馬・中岡晋太郎の周旋により、薩長同盟成立。 |
| 1月28日 |
近藤、伊東、篠原、尾形、小笠原壱岐守ら、再び広島出張。探索方より山崎、吉村貫一郎が先発。 |
| 2月3日 |
近藤ら、広島着。 |
| 2月5日 |
大石鍬次郎、芸州浪人を斬殺。同日、大石の実弟で一ツ橋家家臣の酒造蔵、新選組隊士今井祐次郎に殺害される。これにより大石・今井の間に亀裂が生じ、土方がその執り成しにあたる。 |
| 2月12日 |
勘定方の河合耆三郎、隊費不算の罪により切腹する。 |
| 3月12日 |
近藤ら、帰京。 |
| 4月1日 |
谷三十郎、祇園石段下で殺害される。斎藤一によるものとされている。 |
| 6月7日 |
■幕府軍と長州の間で戦闘開始。 |
| 7月20日 |
■将軍家茂逝去。 |
| 9月12日 |
三条制札事件 この頃、三条大橋西詰の制札場に長州藩を朝敵として批判する制札が立てられていました。が、8月28日夜、十津川郷士中井庄五郎、前岡力雄、深瀬仲麿、豊永植西らが、制札の文字を墨で消した上、引っこ抜いて鴨川の川原に投げ捨てるという事件が起きました。制札は9月2日に再び立てられましたが、5日の夜またもや四人の浪士がやってきて制札を引っこ抜き何処へやら持ち去ってしまいました。
事態を重く見た幕府が9日再び制札を立てるとともに、新撰組へ警備を要請。犯人逮捕の為に、橋の東詰の町家、西側の酒屋、南側の先斗町会所の三箇所に隊士を配置し、さらに隊士二人を乞食に変装させて犯人の再来を待ちます。
はたして12日夜、制札に狼藉を働こうとした土佐藩士八人と、逸早く察知した原田左之助率いる新選組隊士十二人が乱闘!土佐藩士1名斬殺、宮川助五郎捕縛。 |
| 9月14日 |
謀反を企てた見回組大沢源次郎を逮捕すべく、一橋家臣渋沢栄一に伴って土方出動。 |
| 9月19日 |
土佐藩の三条制札事件和解申し出に応じる。 |
| 12月5日 |
■一橋慶喜、15代将軍となる。 |
| 12月25日 |
■孝明天皇、崩御。明治天皇即位。 |
| 慶応三年(1867) |
|
| 3月20日 |
伊東甲子太郎ら十三名、御陵衛士を拝命して新撰組から分離脱隊。 |
| 6月10日 |
新撰組総員の幕臣取り立てが決定。 |
| 6月14日 |
茨木司、佐野七五三之助ら、京都守護職屋敷にて自刃… 幕臣取り立てに対して異議を唱る、茨城司、佐野七五三之助、富川十郎、中村五郎を首謀者とする十名。彼らは伊東甲子太郎が新撰組に残していったブレーンでした。
13日、「二君に仕えるは武士の面目が立たない」と理由をこねて新撰組脱隊の嘆願書を会津藩に提出。これを受け取った会津藩公用方の小野権之丞と諏訪常吉は当惑し、近藤の下に通報します。新撰組から早速、近藤、土方、山崎烝、尾形俊太郎、吉村貫一郎の五人が会津藩邸に出向いて説得に当たりました。
が、埒あかず、翌日改めて話し合いの会合が行われました。この日も一向に決着がつく様子がなく…。すると突然、佐野が中座して別室に茨木、富永、中村の三人を呼び入れました。何やら密談をしている様子であったので、気になった島崎魁が中を覗くと、既に彼らは自刃して果てていました! …しかしこれで話は終わらず、この後怪談のような出来事が起きたといいます。死体を片付けるため佐野の屍の前に座った時、死んでいるはずの佐野が突然立ち上がり、自分の喉を貫いていた脇差を抜いて大石に斬り付けたといいます…(+■+;) 仰天する大石の頬と太股を傷付け、佐野は再びその場に倒れました。傍らにいた志村武蔵らが脇差を抜いて佐野の体を突き通しました…が、すでにぴくりともしませんでした。…しかもその後、駕籠に乗せるために死体に縄をかけようとすると、佐野の口は縄に噛み付いて放さなかったといいます… |
| 6月15日 |
屯所が不動堂村に移転。 |
| 6月22日 |
武田観柳斎、銭取橋付近で新撰組に斬殺される! 元新撰組副長助勤の武田は兵学者で長沼流兵法をよくし、軍師として采配を振るっていました。が、洋式兵制を導入してから武田の立場は揺るぎ、新撰組に居場所がなくなってしまいます。そこで密かに隊を脱走し、分離した伊東に接触をはかりました。が、伊東に拒絶された為、やむなく薩摩藩に接触をはかったといいます。
そんな武田の動きを新撰組は放っておくわけはありません!22日、竹田街道銭取橋付近で武田を肩先から袈裟懸けに切り下ろして斬殺しました。 また同時期、浅野薫が御陵衛士の阿部十郎のもとを頼っていました。浅野は前年の三条制札事件での失策が原因で隊を追放された隊士です。
三条制札事件の折、斥候に立っていたにもかかわらず恐怖に怖気づいて、大石鍬次郎らが詰めていた橋東の町家へ中心するのが遅れた為に五人もの逃亡者を出してしまったのです。浅野は池田屋事件にも参戦した古参隊士でしたが、この失策によって卑怯者扱いされるようになり、後に隊を追放されてしまったのでした…。
それで阿部は親しい間柄だった浅野を保護してやろうと、御陵衛士に加えることは出来ないのでとりあえず山科に潜伏させて、土佐藩の御陵隊に預けることとしました。
しかし、この浅野の不穏な行動もまた新撰組は察知します。沖田総司が追ってとして差し向けられ、葛野郡川勝寺村に浅野を追い詰めました。逃げる浅野に向けて沖田の剣が一閃…。斬られた浅野は桂川に落ちて流されてしまいました…。 ※この浅野薫失脚の過程は異説有り→ 近藤勇不在時に土方歳三によって押し進められた三浦啓之助の松代藩帰藩計画に浅野薫は助力していたものと思われる。が、啓之助の帰藩計画は失敗した上に局長の逆鱗に触れ、一身にその責任を負わされたのではないか?というもの。 |
| 10月14日 |
■将軍慶喜、朝廷に対して大政奉還を奏上。 |
| 11月15日 |
■坂本竜馬、河原町・近江屋で暗殺される。 |
| 11月18日 |
油小路事件 伊東甲子太郎、藤堂平助らを油小路で暗殺。 |
| 12月7日 |
天満屋事件 新撰組、紀州藩士三浦休太郎を護衛して陸・海援隊の残党と戦う。宮川新吉、船津釜太郎、討死。 |
| 12月9日 |
■王政復古の大号令。 |
| 12月16日 |
新撰組、伏見奉行所に布陣する。 |
| 12月18日 |
近藤、二条城からの帰路、伏見墨染付近で御陵衛士の残党に狙撃され、右肩に重傷を負う。 |
| 12月20日 |
近藤・沖田、治療のため下坂。 |
| 明治元年(1868) |
|
| 1月3日 |
鳥羽伏見の戦い勃発!! 新撰組は淀千両松の戦闘に破れ、橋本へ撤退。 |
| 1月5日 |
井上源三郎、淀千両松の戦いに戦死する。 |
| 1月6日 |
山崎烝、橋本の戦いに重症を負い、のち船中で落命する。 |
| 1月10日 |
新撰組、富士山艦・順動丸に乗船して、大阪を出帆。 |
| 1月15日 |
新撰組、品川に上陸。近藤・沖田は神田和泉橋の医学所へ。 |
| 3月1日 |
近藤・土方ら、甲陽鎮撫隊として甲州へ出発。勝沼で官軍と戦い、敗走。 |
| 3月6日 |
この頃、永倉新八、原田左之助が靖共隊を結成して新撰組と袂を分かつ。 |
| 3月14日 |
■御箇条の御誓文、発布。 |
| 4月2日 |
新撰組、下総流山布陣。 |
| 4月3日 |
官軍が流山を包囲。近藤は投降し、土方らは逃走。 |
| 4月11日 |
■江戸城無血開城。 土方歳三、鴻之台の旧幕府軍に参加する。 |
| 4月19日 |
土方軍、宇都宮城攻略する。 |
| 4月23日 |
土方歳三、足に負傷して宇都宮城奪回される。 |
| 4月25日 |
近藤勇、板橋で斬首される。 |
| 5月15日 |
原田左之助、彰義隊に参加して上野戦争で重症を負い、17日に没する。 |
| 5月30日 |
沖田総司、肺結核のため千駄ヶ谷の植木屋平五郎宅で没する。 |
| 8月21日 |
母成峠の戦いに新撰組敗走する。 |
| 9月5日 |
斎藤一、如来堂の戦いで脱出に成功する。 |
| 9月20日 |
桑名、松山、唐津の三藩士が新撰組に加盟する。 |
| 10月12日 |
土方ら、宇都宮・白河・会津などを転戦した後、仙台で榎本武揚の艦隊に乗艦し、蝦夷地へ向かう。 |
| 10月20日 |
旧幕府軍、蝦夷地鷲之木浜に到着。 |
| 10月25日 |
榎本軍、箱館五稜郭を占領。翌日、入城。 |
| 11月5日 |
土方歳三軍、松前城を攻略。 |
| 11月25日 |
土方ら、松前・江差を攻略し、蝦夷地を平定。 |
| 12月15日 |
旧幕府軍、蝦夷地平定の祝賀会を催す。 |
| 12月22日 |
閣僚選出の選挙が行われ、土方歳三、陸軍奉行並となる。 |
| 明治二年(1869) |
|
| 3月25日 |
宮古湾海戦 旧幕府軍、甲鉄艦奪取に失敗し、野村利三郎戦死する。 |
| 4月13日 |
土方歳三軍、二股口の戦いに勝利する。 |
| 4月24日 |
土方歳三軍、再び二股口の戦いに勝利する。 |
| 5月5日 |
土方歳三、市村鉄之助を五稜郭から脱出させる。 |
| 5月11日 |
土方歳三、一本気関門付近で戦死。 |
| 5月14日 |
相馬主計、最後の新撰組隊長に就任。同日、弁天台場篭城の新撰組、降伏する。 |
| 5月18日 |
五稜郭の旧幕府軍降伏。戊辰戦争終結。 |
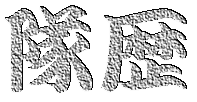
 _。 +*+*+*+
_。 +*+*+*+