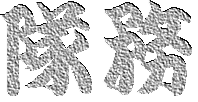
■ 永倉 新八 : 糾弾
糾弾―――――
永倉新八は天保十年四月十一日、江戸下谷三味線堀に生まれました。
幼名は栄治。
父の長倉勘次は睦奥国松前藩士で、江戸定府取次役を勤めた人物。
幼き頃から剣術を好み、神道無念流に八歳の頃入門。
十五歳で切紙、十八歳で免許皆伝を得る腕前に。
十八歳で元服し、この時より名を新八と改めました。
己が剣の道を極めんと剣術修行の為に十九歳で脱藩。
この時、自らの脱藩によって親族に迷惑が及ばぬようにと
姓を永倉と改めたのだそうです。
本所亀沢町の百合元昇三の道場で剣を学び、
二十五歳の時に市川宇八朗…後の靖兵隊隊長、芳賀宜道と
さらなる武者修業の旅に繰り出します。
剣一筋に生きる新八は何時の頃からか近藤勇と知り合い、試衛館の食客となります。
文久三年には近藤勇達と共に将軍警護の浪士隊に参加。
京に上洛して新選組を結成しました。
新選組二番隊組長永倉新八は、数々の武功をあげます。
大阪力士との乱闘から内山彦次郎暗殺、
池田屋事件においても近藤達と共に少数で突入し活躍。
後に禁門の変、三条橋高札事件、油小路の決闘…と
幾多の戦いに参戦してゆくのですが―――
元治元年(1864年)六月五日におきた池田屋事件、
翌月十八日禁門(蛤御門)の変を経て八月。
新八は原田左之助らとともに、会津藩主松平容保公に宛てて
近藤勇の専制ぶりを糾弾する建白書を提出しています。
というのも、隊結成から二年を経て足場が固まってきたところで
近藤の有頂天ぶりに眉をひそめることが多くなったのでしょう。
「あなたの家来になった覚えはない」
後にそう言って江戸引き上げの時に近藤と決別するのですが
この頃から衝突するようになっていったのでしょうね。
一件は容保公に諭されて近藤と和解という形で収拾されましたが、
新八は二ヶ月の謹慎処分を受けています。
故にこの新八謹慎処分中に作成された『行軍録』に
彼の名前は記載されていないのです。
さて、この彼の行動についてですが、糾弾とは
罪状や責任を問いただして咎めることです。
この行為を実行することのなんと勇敢なることか。
現代社会に置き換えて考えてみると余計そう思われます。
最近、不正事項の露見によって手痛い制裁を受ける企業の数々。
その殆どがその企業の社員からのリークによるもの。
…このリーク(leak)とは「秘密を漏らすこと」なのですが
例によって企業を江戸期の武家に例えるならこれ即ち「糾弾」、
ひいては「主君押込」のそれです。
昔は如何にして“家”(=企業)を存続させるかということが最重要課題で
家臣(=社員)は組織のトップ・主君への忠節ではなく、
家の存続如何の為に粉骨砕身していたのです。
主君に忠節を尽くしたとしても、それによって主家が滅びてしまっては
自らの食い扶持を無くすこと(無職状態)になるのですから当然ですよね。
だから主家の存続に有害とみなされた主君は
時として臣下から容赦なく排除の対象とされることさえあったのです。
これが武家社会に置いての正当な実行手段だったのだから流石です。
今ではこの「糾弾」「主君押込」が「リーク」…つまり「ちくり」のような感覚で
捉えられているのだから現代社会の情けなさよ…(T_T)ちくりかぁ…。
武家の出である新八にしてみれば、個人的に頭に来ることを除いても
組の代表である近藤の姿勢を正す為に糾弾するのは当然で
そうすることで己の誠を貫くことは理にかなっているものだったのです。
また建白書をしたためるあたりも武家出ならではかもしれませんね。
そうやって容保公に建白書まで提出して糾弾するということは
新八にとっても新撰組は大切な“家”だったということでしょう。
新撰組を思えばこその行動だったのではないでしょうか?
組織というものはその下に集まる人々の想いの結晶です。
その一欠片として新八も新撰組に誠を捧げていたと思われます。