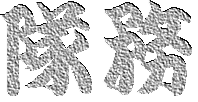
■ 近藤 勇 : 虎徹
業物虎徹―――――
江戸初期の刀鍛冶、長曾禰コテツ入道興里(最初は古鉄、晩年は乕鉄)、
江戸初期の刀工である古鉄は本来甲冑作りが本業だったとか。
が、関が原の合戦の後、越前で仕事を続けていたのが、
初老を迎えて江戸に出て、刀鍛冶を生業にしたのでした。
かの人の晩年の作品、『石燈籠切』はその名のとおり
石燈篭を斬り割ったという一級品であったといいます。
切れ味では多を寄せ付けないと言われ、試し斬りの結果は
中子(刀の柄に収まっている“茎”の部分)に刻み付けて明記されました。
これが評判を呼び、乕鉄の刀は虎徹と通称されてたいそう人気があったようです。
そして我らが局長、近藤勇の業物がその虎徹。
鍔先 二尺三寸五分、反り浅く、肉厚く、刃紋が大みだれにみだれ、
朴強の感、骨を噛み砕く凄味…。
朴咄さが近藤に似通っていたといいます。
鍔は武蔵鍔で、従来は八角の肉厚の銅なのですが、
近藤さんの場合こしらえは鉄であったようです。
が!この差料は贋物だったのでは…?ということが囁かれています。
現物が残っていない上に、(兼定のように残っていればなぁ…)無銘であったようで、
又、この虎徹を入手した方法が幾節かある為だと思われます…
拙者は司馬遼太郎氏の『新撰組血風録−虎徹−』で描かれてある通り、
賊を成敗した礼として、鴻池家から貰ったという説と、
斎藤一が京都の夜店で見つけ、
それを近藤に譲ったとする説を信じきっていたのですが…
(作中では本物の虎徹を見付けて来た斎藤に、
土方が「隊の為だ」と死蔵してしまうのですが)
鴻池家から貰ったというのは、壬生浪士組結成直後、
大阪の鴻池家に押し入った覆面の武士を発見し、
同行していた土方(又は沖田かも?)と斬って捨てたところ、
礼として貰ったという物なのだとか。
このエピソードは『両雄士伝』にも綴られており、
名刀一口を謝礼として受け取ったことが記されているようなので
虎徹は本物だった可能性もありますよね。
そして、刀剣の目が利く斎藤一が京都の夜店で偶然見付けたというのは…
これは胡散臭い説ではないでしょうか?
…いや、偶然ということは偶然あるかもしれないということで可能性は無きにしも非ず…
他の入手説はといえば、
新撰組としての活動が認められてから、徳川家より拝領したという説。
…これも胡散臭い…と拙者は思いますよ?
拝領するような手柄はありましたから貰ったかもしれませんがね…?
他に考えられるのは、上洛前に買った偽物の虎徹を
本物だと信じ切っていた…というようなことぐらいでしょうか?
こう言っちゃナンですが…これが一番ありえそう…(笑)
実際、当時虎徹の贋作が蔓延っていた為、
本物を見付ける方が難しかったというほどですし。
ま、このように諸説あって何が本当やら分からないのが実情。
でもね、本物にせよ贋物にせよ、
この“無名”の差料は多分な働きをしたのですから上等。
池田屋騒動の折、局長はこの剣を持ってテロリストに鉄鎚を下した時のこと。
「下拙の刀は虎徹故に候哉、無事に御座候―――」
池田屋事変直後に故郷へ送った手紙にそう記し、
この一文で自分の刀が虎徹であることをほのめかしています。
共に戦った沖田や永倉の差料は曲がったり折れたりしたというのに、
近藤の刀は頑丈なもので、刃はぼろぼろになっても
従来どおり鞘にすっきり収まったというのです。
当人の腕が良かったからということもあるっでしょうが
やっぱり刀の技量に加え、刀の質も良かったのでしょう。
まさかに、使用しなかったわけではありますまい…
いくら良い刀でも下手な扱いをすれば刀は折れますしね。
日々、命の遣り取りをする新撰組なのですから、
自らの命の盾ともなる刀においては、
粗悪な物など使うわけにはいかないのが当然でしょうよ。
ましてや局長の腰に召すものなのですから、それ相応の物を使用したはずですよね。
元は浪士隊参加に望んで用意したもので“無名”の刀だったかも知れません。
しかし京に上って市中の取り締まりにあたり、
壬生浪士組〜新撰組の存在が世に馳せて、
“無名”の刀が過大な価値を帯びたとしても不思議はありませよね?
それが譲り受けたり、授かったり、見つけたりした物であれ。
近藤さんはとっても虎徹を気に入っていたというのですから
贋物だなんだというような野暮は言いっこなし。…というのが拙者の本音(^〜^)>