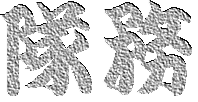
■ 土方 歳三 : こぼれ話
2002.06.23総司忌の折に講演会で伊東成郎氏から伺いました
土方歳三に纏わる御話の断片をいくつか御紹介。
総司忌なのに歳三談義とはこれいかに?
土方FANなる拙者には有り難いことでございましたvvv
土方家御子孫の方が残された手記や、活字本からの抜粋資料も
講演会では配布されたのですが、こらの掲載は出来ませんので、
D×Iの記憶するところをちょいちょい綴らせて頂きますね!
土方さんのエピソードに偏ってます。。。へろり…☆
▽
▽
▽
さてまずは、土方歳三を取り上げて新撰組・歳三FANにとっては
夢の様な対談が持たれた事があったということ。
それは司馬遼太郎と子母澤寛という新撰組二大作家による対談。
そこで語られた二人の会話にこんなものがあったとか…↓
子母澤 「土方さんは多少は文才がありますけれど〜」
司馬 「二流川柳作家程度の文才ですね」
すわっ(‘_‘;) …そこまで仰いますかっ!?
御二方ほどになると土方さんもこう語られるのですね(笑)
▼
▼
▼
そしてっ、地元ならではの日野に語り継がれる
幼少期の歳三エピソードを伺うことが出来ましたv
高幡不動尊の御住職からお聞きしたという御話。
どうやら歳さんは高幡不動尊の山門がお気に入りの場所だったらしいのです。
豊玉発句集に綴られている 「山門を見越して見ゆる春の月」 の一句。
あれは高幡不動尊のこの山門を詠んだのでは?
といった見解も伊東先生から伺いました。
もうっ、そんなこと聞いちゃったら上りたくなるじゃないですかっv
いけませんよっ真似しちゃっ。
バラガキと呼ばれた典型的ガキ大将な幼少期の土方さん。
ナントカは高い所が好きだと申しますが…
彼も高い所が好きだったようで(くすりv)
皆の面前でこの山門によじ登ったそうです。
…罰当たりなことこの上ないですね…
そんな悪童の挙動に制止の声もあがり…
しかしそんな制止など聞く耳持たないバラガキ歳さん→( ̄^ ̄)ケッ
しっかり登って何を仕出かすかと思いきやっ、
山門にあった鳩の巣から卵を掴み取って
見守る人々に投げつけたんですってっ! 大爆笑っ!!
流石っ歳さんっ☆ やっぱり幼少時からして常人じゃないね(笑
きっと試衛館でも枕投げとかしてたでしょうね(笑)
はっ、でも昔の枕って当たったら痛いッスね…。

また、そんな歳さんに毛色の違うエピソードが一つ。
ある葬儀に御手伝いに行った歳さんは下足番を任されたんだそうです。
バラガキのことだから葬儀の席でも何か仕出かすかと思いきやっ、
なんと一足も間違えずに返したとか。
記憶力が優れていたのですね。
只のバラガキではないということです!馬鹿にするなってね。
それに悲しい席で悪戯するような奴でもないですよ。
やっぱり歳さんは良識あるバラガキだったのですね(支離滅裂)。
伊東先生の談によれば、こんな下っ端仕事が妙に達者な人が上司だったら
きっと副長直轄の監察部隊は精鋭揃いだったでしょう。
…とのこと。…確かにそうかも…と妙に納得( ̄▼ ̄)>
そんな才能を持っていたものだから人を動かすのは上手だったといいます。
村の人達の協力の元に家伝薬の原料である牛革草を
刈り取る作業の指揮をとっていたというエピソードは有名ですよね。
が、追々年齢と共に農事手伝いを極度に嫌うようになったとか。
野試合を開いては毎日を遊び暮らしていた〜というような記録が残されているくらい。。。
遊び暮らしていたって…(汗
▼
▼
▼
で!これは新情報だろうってのを教えてもらいましたよ!
なんと薬の行商には同行者がいたというもの。
毎日を遊び暮らしていたというバラガキ歳さんは、ある時「一策を案じ」て
嫌いな農事の変わりに家伝薬の行商すると言い出しました。
「一策を案じ」とはお兄さんの言葉にあるようなのですが、
…信用されていなかったのでしょうね…
なんと石田散薬の行商にはお目付け役が付けられたのです。
これまで一人行商で道をズンズカ歩く歳さんの姿しかイメージに無かった為、
お目付け役と二人して行動していたという事実に驚き。
しかもそのお目付け役というのは…
その名も通称「酒屋の爺さん」…つ、通称もなにも…。。。
ツズラ箱に石田散薬を入れて、剣術道具一式も担いで
この爺さんを共に、行く先々で他流試合を申し込んでは剣の腕を磨いたのだそうです。

御存知、酒で飲む妙薬、石田散薬。
これを爺さんの酒と歳さんの薬でワンセット販売しちゃうとはっ
この商売上手っ☆ 誰の作戦だ? 歳さんか?
歳さんは酒は飲まないから商売物に手を出すこともなく、
酒屋の爺さんとは良いコンビネーションだったでしょうね。
また、放っておけばまたまた暴れ出しかねないバラガキ歳の
ストッパー(リミッターか?)としても爺さんは役目を果していたのでしょうね。
根は優しい歳さんだからvvv 爺さんと一緒なら無茶はしないでしょう。
…とすると目付け役をつけたお兄さんの作戦勝ちですか。
因みにこのエピソード、歳さんの十五・六歳の頃のことだそうです。
行商の帰り道、歩き疲れた爺さんをおんぶして帰る歳さんを
思い描いて微笑ましく思うのは拙者だけでしょうか?
▼
▼
▼
さてさて上洛してからの御話に移ります。
清川八郎らと京洛に上るも浪士二派に別れて京に残りし
後の新撰組となる彼等は壬生に居住したことから“壬生浪士”と呼ばれました。
が、その通説の「みぶろう」と呼ばれた彼らの同時代史料に
“芹川浪士”と記されたものがあると示して頂きました。 …芹川?
そうです… 芹川→芹澤 ということですよ。
初期の新撰組は芹澤派の印象が強かったということなのでしょう。
芹澤派と近藤派は京洛でも明らかに区別されていたのでしょうね。
きっと組の代名詞みたいに“芹澤浪士”なんて呼ばれて
悔しかったでしょうね〜…特に土方さん…。
だからこそ組織体制の改革で粛清には非情でしたし、
自ら鬼となって新撰組の組織を育て上げたのです。
先に触れた様な微笑ましい歳さんの逸話が残されていることから察っせられるように、
歳さんは皆から愛される少年だったので、
日野では新撰組の鬼と化した土方さんは想像も出来なかったようです。
▼
▼
▼
で!今回の公演のメインだった加納惣三郎の御話。
加納惣三郎といえば『新撰組血風録』の「前髪の惣三郎」で御存知!
前髪立の美剣士による耽美物語…映画『御法度』でも紹介されました。
内容は衆道(男色)気の強い物語なのですが、
この元になった逸話はちゃんとあって、それは全く衆道とは無縁の御話。
確かに男色が隊内に流行ったのは事実のようですが
加納惣三郎に関しては司馬遼太郎さんの創作なので御注意。
さて、その元になった逸話というのは
加納惣三郎が女性関係で隊から制裁を加えられたというものです。
惣三郎は健全な男子だったのですよ。
しかし「前髪の〜」と同様に惣三郎は美しい少年だったそうです。
しかも京女からは「今牛若」と呼ばれて恋されたのだとか。
当時代版牛若丸よろしくな美少年だということですよ。
その美しい惣三郎は商家の息子として生まれたのですが
武士に憬れて剣を学び、若年ながらも新撰組に入隊。
近藤さんもえらく可愛がったようで、隊内でスピード出世を果しました。
が、その出世が気の緩みをもたらし、
いつしか覚えた遊郭での女遊びに深入りして
郭通いの遊びの金欲しさに、ついには辻斬りをはたらくように…。
こうなっては隊の面目にかかわることです。
惜しき若者であっても捨て置くことは出来ません。
そこで、せめて汚名が残らぬように人知れず討ち果たそうと
小太刀の名人であった田代に密命を下したのでした。
が、返り討ちにあってしまったというのが「前髪の〜」の元ネタ。
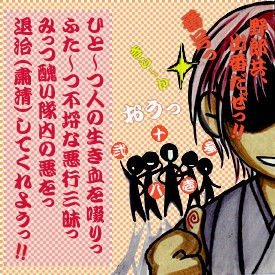
で、結局どうケリをつけたかといえば土方さんの御采配。
是が非でも討たねばならないと盟友である近藤さんに頼まれた土方さんは、
大ハリキリで腕利き五・六人に惣三郎討ち取りを命じました。
郭からの朝帰りの時を待って、屯所の塀を飛んで入ってきたところに
惣三郎は斬り殺されてしまったという顛末であります。
ここで伊東先生に気付かされましたのは、土方さんが直接手を下していないということ。
局長の命であっても自らは采配を揮うのみ。
必勝の手配をするのが何より楽しい人なのですって。
さて、その腕利きの五・六人…やっぱり豪華メンバーで決まりでしょう。
番号っ☆ 壱、弐、三、八、十ってところですか?
芹澤一派暗殺メンバー +α の再結成だったのでは、という予想。
そして物陰に検分役で土方さんがいるという構図です。
むむむ、暗殺となるとやはり信用のおける腕利きでなきゃいけませんからねぇ。
▼
▼
▼
で、もう一つこの惣三郎の逸話には貴重な記述が。
新撰組のユニフォームであったという有名なダンダラ羽織。
実は粗悪品だったらしく三ヶ月程度しか使用しなかった上に、
幹部連中は着用されなかったらしいですね。
では彼らの格好はどのようなものだったかというのが、
惣三郎の巡回場面の記述に記されていたのです。
“黒羅紗筒袖の陣羽織”
黒装束だったんですね。 …黒…黒…黒といえばっ
土方さんですねっvvv 一張羅の黒羽二重vvv
紅い面紐を用いるような御洒落好きな土方さんのことだから
万一、自分が着る事になっても見栄えが良いように
自分に合わせて作ったのだろうという予想。
ありえることです。。。紅い面紐だった人ですし(笑)

最後は箱館戦争の際の箱館山でのエピソード。
彰義隊隊士であった寺沢正明さんの記録からだそうで、
この方は土方歳三の最期を見たのだとか。
記録によれば、箱館山の占拠されまいと新撰組隊士を置いて行ったといたというのに、
うっかり(うっかりって…)占拠されたとの報せを聞き、
地団駄を踏んで残念がり、マジギレ状態で「新撰組の雪辱は俺が晴らす!」と宣言するや
制止を振り切って、馬で箱館山に攻め上ったところを
人馬もろとも銃弾に倒された… というものなのですが。。。
添えられた文句に抱腹。
一人で登るのも大変な箱館山を、中腹まで馬を駆って登った勇姿は末代まで誉れを留めた…
って、誉って。。。 ぷくく〜。。。
脳裏に浮かんだのはドン・ボナパルトよろしくな土方さん(笑)
これじゃぁ、一本木関門で頑張った大野さんの立場はどうなるの?
本気のことなら、この戦況眼が彰義隊の敗因じゃぁないかと思われる…
そうコメントされた伊東先生の言葉に講演会参加者一同頷く…(嗚呼。
日野時代、人の制止を振り切って山門を登った少年が、
後に制止を振り切って箱館山を登る男に成長する〜
というオチで締め括りです☆ べべん♪