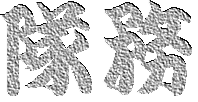
■ 原田 左之助 : 死に損ね
快男児―――――
天保十一年、伊予松山藩の足軽、中間を勤める藩士、
原田長次の長男として生を受た左之助。
左之助が十五・六歳の頃、藩邸で小使いをしていた時の
藩邸にいた人の後日談によれば“なかなか怜悧な男”であったといいます。
が、根が剛胆だった左之助は、素っ裸に褌ひとつでほおかむりをし、
オランダ式の銃隊で使う太鼓を首から下げて打ち鳴らしながら
上士の住む屋敷町を歩いたという話もあるので、怜悧の意味を調べ直したり…。
また、その剛胆な性格から、目上の者にも傲慢で言うことを聞かなかったとも。
その為に制裁として集団リンチを加えられたこともあった、
という奇行も伝わっています。…それでもやはり生意気だったとか。
安政三年頃に江戸の松山藩邸で中間として働いき、
国元に戻ってからは若党になり、
後には江戸の三田藩邸などに取り立てられたりもしました。
仕事はキッチリしていたのでしょう☆ が、この間に
この時代の男のステータスとも言うべき“呑む・打つ・買う”
は全て錬磨していたというのですから…悪い友達がいたのでしょう。
この一歩間違えばキ●ガイと紙一重な(失礼っ)原田左之助という青年の持つ
常人には無いもの、といえば腹の傷!切腹の傷痕です。
「切腹の作法も知らぬ下司野郎」と罵られたのに憤慨して
腹を切ってみせた、という名残の品なのだそうですが…
余程腹に据えかねる物言いだったのでしょうね?
カチンッときたくらいで腹は切れんよぉ(+_+;)原田さんっっっ(焦)
手当が良かったのか生命力が人並み外れていたのか
切腹したにも拘らず、なんとか左之助は一命を取り留めます。
後の新撰組活動期に娶った左之助の妻、おまささんの話では
その腹の傷を自慢げに叩きながら“駕籠の中で切ってやった”と
左之助は話して聞かせてくれたと言いいます。
この切腹エピソードを綴った小説や物語の多くがありますが
どれも往来で腹を切ったものとなってますね。
駕籠の中で切腹というのでは、フィクション的に
彼を描くのには一味掛けるのでしょうが、
この駕籠というポイントは特に切腹に関係するものではないのでしょうか?
例えば、「切腹の作法も知らぬ下司野郎」と罵ったのが上士で、
その駕籠に乗り込んで“嫌がらせ”に腹を切ったとか…どうでしょう?
その前にこの罵りが切腹に至る引き金だったと言うのは本当なのでしょうか?
本当であれば“切腹の作法も知らない”ということを馬鹿にされて怒ったのか、
“下司野郎”にカチンッと来たのか……(+_+)
って、どうせその両方にムカッとしたのでしょうが。
しかし“切腹”というものが会話で語られるこの時代、
どれだけの重みを持っていたのかがここでも伺えますね。
武士の社会で“切腹”は無くてはならないものだったのでしょう。
武士にしかないものだからこそ切腹は、
武士としてのステータス保持的存在でもあったと思われます。
だから武士の死に際において切腹はありがたい死に方であり、
逆に斬首などといった処刑は
「お前は“武士として”など殺してやるものか!」
といった意味を持っているわけで…
近藤さんの板橋処刑がその例です(悔っ)
そう考えると原田さんが切腹に及んだこの珍事件も
「俺は武士だからなっ」という思いが
多分に叫ばれているものだと感じられますね。
その者の切腹を笑うは、その者が武士であることを笑うと言うこと。
だからここで罵られたのも
「お前が武士だって?笑わせるな、ケケケッ」
といったニュアンスが含まれていたので、
原田さんは切腹して見せたというのではないでしょうか?
「俺はこんだけ立派に切腹できるんだぞ!笑えるものなら笑ってみろっ!」
くらいの気合で刀を突き立てたはずです。
口で言うより体現して見せた左之助切腹珍事件。
左之助の気性と漢ぶりを感じさせられるエピソードの一つです。
この後ら辺で脱藩して、江戸で試衛館道場に転がり込むに至るのですが、
そこらへんの詳しい経緯は不明。
槍を携えた脱藩浪人の左之助が試衛館の食客となるまで…
やはり槍の修行をしながら放浪していたのだと思われます。
酔っぱらうと前をはだけて腹を出して、ぺたぺた叩きながら、
「金物の味を知らねえ奴なんぞとは違うんだ」と言って
切腹の跡を見せていたというのですから
きっと放浪期にもこの逸話を聞かされた人は多かったかも?
新撰組とは関係無しに、何処かで語り継がれてたりしませんかねぇ?